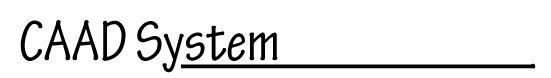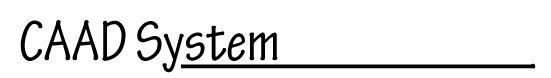

1.様相とは何か — 様相をめぐる2段階の課題
私は、現代建築を様相なる概念を明らかにしてゆく過程であると考える。
近代建築 機能 身体 機械
現代建築 様相 意識 エレクトロニクス装置
現代建築の活動は多様であることにその意義と特性があり、この傾向は持続されてゆか
ねばならない。上記の対比表は、未来の視点を今日にあって先取りし、自己批判的に建
築家の活動を拡大しようとする試みである。
様相をめぐる課題としては、現代建築全般ないしはより広く理解すれば、現代の文化全
般にわたる巨視的課題と、極めて微視的な課題である私個人の建築表現における課題と
の2つの局面がある。
(1)様相についての一般的課題
今日、私たちは建築あるいは都市について次のような新たな関心をもっている。例えば
(イ)家並み、町並み、より広く言えば景観をどのように分析したり、分類したらよい
か。(ロ)建物の全体的な印象としてのたたずまい、雰囲気、気配をどのように記述し
たらよいか。(ハ)地域性、場所性といった事項が議論がされるが、それらは何によっ
て表記されるのか。(ニ)圧迫感、心理学的距離、活動のテリトリーといった環境心理
的な現象は、いかにして記述されるか。(ホ)都市や建築の様子の時間的変化、あるい
は変化の周期性はいかにして捉えられるか。といった関心がある。……これらの関心は、
直感的にいって機能論によっては解決されない。
何故かといえば、ひとつに、これらの課題はまず第1に、都市や建築の性状、あるいは
状態を全体的に指し示そうとしており、今日その状態を表現する言語や方法に欠けてい
るからである。第2に、これらはもともと人々の体験的な記述であり、人々の意識にか
かわっているからである。
上記の事例が指し示しているものや空間の状態が、様相なのである。そして、上述した
文章で全体的と体験的とは、実は同義なのである。様相(mode, modality)なる概念
は、古くはアリストテレスからはじまり、近代になってロックやカントが言及し、今世
紀になるとパースやバルトが論じており、今日では様相論理学、可能世界意味論などで
もっとも中心的な話題となっているのは周知のところであろう。こうした歴史のなかで
ロックにみられるように、様相を性状ないしは状態として経験的にとらえる傾向と、ア
リストテレスやカントのように様相を〈可能態〉としての状態ととらえる傾向とがみら
れる。そこで私たちは、まず今日の様相論理学、可能世界意味論などの関心にあわせて、
様相を状態の〈可能態〉としてとらえることにしよう。単純に言えば、「空間が次の瞬
間にはどう変化する可能性があるか」、「10年後にはどう変化している可能性がある
か」といった問いを含んだ現時点でのものあるいは空間の状態が、様相なのである。し
かし、こうした動的変化の観点だけでは、様相の一面しかとらえていない。〈可能態〉
は、単なる物理・科学的な予測の対象にとどまらず、観測者の体験の可能性の記述であ
るのだから、観測者自身も「次の瞬間」あるいは「10年後」、意識は変化しているの
である。かくして様相論的考察は、現象の可能性についての考察であるが、それと同時
にその現象にかかわりながら生きる人間の構想そのものを対象にすることになるだろう。
上述の(イ)から(ホ)のような問題は、こうした様相についての認識をもってしない
かぎり、解決できないどころではなく、問題にとりくむこともできないだろう。建築の
デザイン活動にあっては、様相に関する一般論から離れて、様相の具体的な表現こそ重
要である。
(2)様相についての今日の表現活動における課題
今日、私たちはデザインについて次のような共通の関心をもっている。(a)ハイテッ
クといった語で形容されるフィーリング、雰囲気の表出。(b)近代建築を通して養わ
れてきた事物の構築法、配列法とは異種の、それらの発見 — これらを「構成の廃棄」
といってもよいだろう。(c)混成系の表出。(d)表層性、複雑さの表出。要素のも
つ意味とそれらの文脈的あるいは非文脈的表出など。(e)メタフォアの形成、記憶の
誘導。……以上、思いつくままの列記であるが、これらは機能論的関心というより様相
論的な関心である。
つまり建築は表現課題のもつあいまいさにおいて、〈可能態〉としてみなされる。様相
論理の記号を象徴的に応用すると、必然性□(スクエア)と可能性◇(ダイヤモンド)
とが、同時存在するようなかたちになる。
こうした状態を、直感的に、一気に空間のモデルに転化すると次のようになる。
(*)境界があいまいな(事象の)様相
この図式化は、□を「境界がさだかである」、◇を「境界がさだかでない」と置換した
結果であると解することができる。従って(*)の意味は、「境界があると同時にない」
であるとも解釈できる。いずれにせよ時間的なアンビギュイティを、空間的な装置へ移
行させるプログラムである。
境界と可能性の関係は、例えば「ファジィ集合」のメンバーシップ関数によって示され
る。
(*)は、また、意識表現のひとつの側面を表現しようとしている。ある場所の体験は、
その場所の過去における体験と意識現象において重なり合う。過去の体験は記憶として
意識のなかに蓄積されているが、記憶が場面や情景といった図像の形式をとっていると
き、これを〈情景図式〉と呼べば、この図式は眼前に展開している情景に比べて、極め
てあいまいな図式となっている。これも比喩的に言って、境界がさだかでない図式なの
である。
こうして、(*)は、物的現象と意識現象のひとつの側面を二重に照らし出すための表
現目標となる。この表現目標は、(1)で述べたような課題に対する解答を出すのでは
なく、問題の所在を訴える意味しかもたないであろう。しかし。芸術や建築の表現とは、
もともと。時代の課題を照明するというかたちでのみ成立するのである。
2.「境界をあいまいにする」方法としての〈多層構造〉と〈経路〉
これまで、「境界をあいまいにする」ための方法について試行を重ねてきたが、主とし
て展開してきた方法は〈多層構造〉であり、この方法の建築的な効果は、〈重ね合わせ
overlay 〉であり、とくに〈映りこみによる重ね合わせ〉であった。
多層構造のモデルとして『意識の様相論的空間』の装置がある。これは24台の光学的
な〈楽器〉からなる図像生成装置である。この装置の機構は、さまざまな光源と透明ア
クリル板状の発行部分がつくる図像の多層的な重ね合わせを生成する。つまり、光の装
置を時間的に楽器のように操作して、〈さまざまな部分の重ね合わせによって、継時的
に発生する場面の総体がつくる様相〉を抽出するのが目的である。この装置は、図像が
重ね合わされてつくられていることから、視点の位置によっても図像が異なっている。
言い換えれば、(*)の目標のモデルであり、建築という物的現象と意識の現象とを同
時に示すひとつのモデルなのである。
この装置を使って、一連の図像の重ね合わせの13分39秒間のひとつの光学的な〈曲〉
を作ったが、この〈曲〉を建築的に言い換えれば〈経路〉である。また、この装置を建
築とみなし図像が〈情景図式〉であるとすれば、次のような定式化が導かれる。即ち、
(〜)建築は情景図式の経路化である。
この経路化された体験の総体が、建築の様相であると考えることができよう。私たちが、
ある建築を体験する全過程を考えてみよう。常に住んでいる住宅から、一度しか体験し
ないで終わる建物にいたるまで、その体験の構造は(〜)で表記できる。
例えば、〈経路〉は均質空間のように常に空間が一定の状態に保たれるように計画する
こともできるし、相互に差異のある特性ある空間を次々と通過してゆくように計画する
こともできる。後者の建築は、いわば〈混成系〉の建築であり、異質の空間が同時存在
している建築である。シュールレアリスムのコラージュの手法の理論的基礎となるロー
トレアモンの図式、即ち「手術台上のミシンとこうもり傘」にちなんで、異質の要素か
らなる要素の集合を〈ロートレアモン集合〉と呼べば、混成系の建築はなんらかのロー
トレアモン集合からなる建築で、人々はこの集合を横断してゆく経路を体験することに
なろう。
要約すれば、上記の対比例は単調な経路をもつ建築と、複雑な経路をもつ建築とがあり
うることを示しており、ここでは後者の建築の実現を目標にしているのである。これは、
様相についての端的な対比ともなっている。混成系の建築が、極めて多種多様の要素か
らなる場合は、そのつど道すじのとり方を変えれば、総体としての経路は複雑に組み立
てられるであろう。興味の尽きない都市はその好例であり、楽しい美術館、博物館、遊
園地といった建築もその例である。しかしながら、小さな建築や付加物がない建築にあ
っては、そうした経路の計画は難しい。一般には、そのつど出現する出来事が、経路の
単調さを救ってくれている。従って、出来事のプログラミングは極めて重要である。ま
た、建築を様々な出来事が誘起されるように計画することが、建築家にとっては直接的
な仕事となる。特に公共性の高い領域についての計画が大切である。
さて、混成系の程度に限界がある場合、ひとつの建築において多様な空間の状態を誘起
する方法として、外界の変化にあわせてファサードや室内の状態を時間的に変化させる
方法が考えられる。単純な例は、スカイライトをもつ部屋がそうである。自然光の変化
に応じて部屋の状態も変化する。このような建築は、〈応答する corresponsive〉
建築と呼ぶことができる。広義に解釈すれば、人々の活動から生まれてくる出来事を誘
起する建築、それら出来事に呼応する建築も、この概念に含まれるであろう。
多層構造が生みだす情景図式は、複雑な経路を生成するうえでやや異なった効果をもっ
ている。それは、基本的には『ミネアポリス・モデル』がもつような視点の位置におけ
る図像の変化である。
3.様相論的建築をめざして
様相なる概念は、ある経験を分解しないことを指示する。もし、連続している経験のな
かから、ある経験を指し示そうとするなら、そのための分節化は時間のうえでなされる。
ある経験は、特定な時間内になされた経験として抽出されるのである。もちろん、その
抽出された経験の内容と意味を示すためには、空間的に説明されなくてはならないだろ
う。しかし、その空間的な説明は、便宜的であるにとどまり、現実の体験はいかなる言
語あるいは記号的記述にも還元できない。様相は、経験のもつ完結性を保存するための
概念である。
従って〈経路〉とは、空間的な組み立てではあるが、経験に則して言えば、分節しうる
時間的な体験の連鎖である。出来事の系列あるいは過程である。建築や都市を計画し、
設計する立場からすれば、それぞれの個人が固有の経験の総体を持つことを認めると同
時に、それらの経験が多様であることを目標としなければならない。そして、それぞれ
の個人の経験は、生きている限りにあって〈可能態〉であることを踏まえて立たなくて
はならないだろう。(〜)で検討した内容を一般化すれば、可能態としての経験には、
惰性的展開と発見的展開があることを示している。現代建築がめざすのは、あらゆる人
々の生きる経路が発見的展開の形式をもつこと、この条件を環境のうえで整備すること
に他ならない。付言すれば(*)の命題は、多くの可能性の障害となっているさまざま
な境界、たとえば国家の境界、人種あるいは民族という境界、既成の制度等々の境界を
あいまいにしてゆく方向を示唆している。現実を見据えれば、これらの境界は厳然とし
た事実として、また強力な規則力としてある。しかし、それらは「あると同時にない」
かたちにもってゆくことはできるのでる。
今日、エレクトロニクスの時代はシミュレーションの科学を準備している。その意図は、
経験の全体性を保存しつつ〈経路〉を組みあげるところにある。時代は、あきらかに機
械からエレクトロニクスに移行した。しかしながら、機械のような建築の近代建築の理
念にあわせて、エレクトロニクスのような建築を直接的な目標とするわけにはゆかない。
何故なら、エレクトロニクスはものではなく出来事に対応しており、建築はあくまでも
ものを組み立てる作業であるからだ。私たちが長い間語ってきた空間であるとか、空間
の効果が、まさにエレクトロニクスの効果と対応している。そこに新しい地平が開かれ
る余地がある。
経路の発見的展開は、当然ながら新しい体験を準備する建築を社会に提供する作業が基
本となり、この原則は、これまでの建築の歴史を通じていささかもかわるところがない。
今日、技術は飛躍的な展開を見せ、これを応用することによって人々の建築的体験の幅
はますます拡張されるであろう。と同時に、様相論的建築は多くの人々を受け入れなが
ら、それぞれに異なった情景図式を記憶として持ち帰る体験の総体を誘起してゆくであ
ろう。