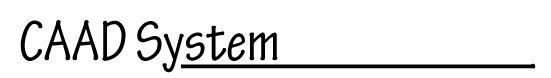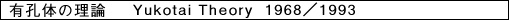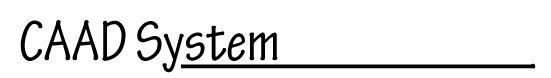
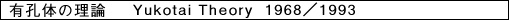
〈有孔体の理論についての概略〉 1968
有孔体の理論は
1)上から全体性を規定する方法
2)部分 あるいは個の平均化
3)非論理的な多様性
を否定し
1)下からの全体性 連帯を構成する方法
2)部分の自律性 論理的な多様性を実現するために提案され、社会構造の理念
と環境形成の理念とが同化することが期待された。
有孔体の理論において重要な概念は
1)空間単位 単位=個となる空間領域
2)被覆 空間単位を包む境界面 BUILDING ELEMENT
3)作用因子 運動するもの
4)孔 作用因子の運動を意図的にコントロールする装置
有孔体の理論は
1)有孔体の単位の搾孔作業
2)単位の結合作用
なるふたつの計画内容を指定する。
有孔体の単位は次のような事項にもとづいて計画される。
a)道具類によって行為が決定された領域と自由浮遊の可能な領域とを計画する。
b)有孔体の孔は、実証的な要求条件にこたえるべく搾孔される。また環境的な
空間効果をあげるべく搾孔される。
c)有孔体の単位の被覆のかたちは孔と自由な領域の設計によってゆがめられる。
d)有孔体の孔は、作用因子に従って自律的にあけられる。それ故有孔体の単位
は〈ずれ〉の総体である。
e)有孔体の孔は空間の方向性を決定するシグナルとしても計画される。
有孔体の単位の結合は次のような事項にもとづいて計画される。
a)有孔体の単位間におこる作用因子の運動の必然的関係に従う。
b)有孔体の単位の集合はそれ自体有孔化する。
言いかえれば、自由な領域と孔をつくる。
c)有孔体の単位の孔の集合は、単位の集合の空間的環境的構造を表示する。
有孔体の理論の実践は
論理的に見て絶対に不完全な上述の理論に従い空間制御装置として有孔体らしい
ものの発見によって決定にみちびく。
〈補遺〉 1993
[有孔体の理論は…とが期待された]に対応して
きわめて意図的な建築のほとんどが、全体から部分へと下降する方法によって
つくられる。
⇒この種のデザインは、当初に与えられた諸条件を検討し、そこから最も
適切な全体的パターンをつくり、再びそのパターンから部分へと下降し
てくる。
もちろん、全体的パターンは部分的検討によって修正されるという作業
がともない、下向(分割)と上向(構成)が繰り返されるであろう。し
かし、初期において全体的パターンを与えるという方法は、おそらく形
式主義的建築を生み出すであろう。
均質な空間を支えている理念は、
「ア・プリオリな原理によって各部分を統御する原理のもとに、個人は全面的
に従わねばならない」
という社会理念に呼応する。
⇒均質な人間は、識別ができない。それは建物相互の識別ができず、建物
内で自分のいる位置がわからないという事実に通じる。
形式的な建築は、統一の美学に根ざしている。
都市的スケールでみれば、多様の統一の美学があるが、ひとつの建築について
みれば完結性の美学である。
こうした統一の美学からは、なかなか個=部分を保存する建築は生まれてこな
い。
⇒建築は人びとが簡単に拒否できないから、そのよってたつ美学はすでに
確立した美学、人びとが慣れ親しんだびがくでなくてはならないという
要請がある。それだけに統一の美学をやぶるのは難しい。しかし、統一
の美学に依存する限り、部分は圧迫されざるを得ないのである。
箱型の建築や、形式が優先される建築は、内的な組織、あるいは空間を被覆す
る性格をもっている。
⇒被覆性は、現代建築の特色であるばかりでなく、現代文明の特色でもあ
る。
全体性 → 被覆性
科学 — 自然の被覆性、人間の心理の被覆性を打破。
宗教 — 被覆の働きをもつ。
被覆は全体を了解するために発見されたシンボル的手段。
被覆は、結合可能な〈活性化した〉被覆、言いかえれば積極的にある側面で結
合し、他において結合を拒否する意志を表明する制御体でなければならない。
⇒これが主体性であり、制御体の形成が個を他と区別する唯一の手掛かり
となる。
かくて、被覆の概念は本質的にうちやぶられ、露出性が優位にたつ。露出性ゆ
えにわれわれは様々の存在の個別性を知ることができ、統一や完結の閉鎖性を
のりこえて、異質なものが共存し矛盾を容認できる美学への足がかりを得る。
[有孔体の理論において重要な概念は]に対応して
社会における個人と対応する建築的な基本単位として、閉じた領域、閉じた空
間単位(通常的には部屋)をとる。
被覆は、この空間の外皮すなわちビルディングエレメントの集合である。
この被覆に作用する様々な因子、空気・光・熱などの自然要素や、各種のエネ
ルギーや情報、こうした運動するものどもに対応して、孔がうがたれる。こう
して閉じた領域すなわち〈死の空間〉は、搾孔作業によって〈生の空間〉へ転
化する。
[有孔体の単位は]に対応して
有孔体の単位空間は、〈閉じた空間〉あるいは分節された領域に対応して設定
される。
このとき、領域は大別してふたたつのカテゴリー、すなわち〈決定領域〉と〈
浮遊領域〉に分けられる。
〈決定領域〉に対する搾孔作業は合理性に依拠するが、〈浮遊領域〉の場合は、
必ずしもそうではなく、理論的には規定しきれない。いずれの場合もなんらか
の空間効果という美学的判断が介入する。
空間単位すなわち初源的な〈閉じた空間〉は、抽象的な閉じた境界面すなわち
被覆をもっているが、その被覆は、領域の検討、特に〈浮遊領域〉の設定と作
用因子の処理(例えば、雨とか風)、なかんずく外界との交通のための孔の設
定によって形態が決定されてゆく。
搾孔作業は、室内の環境条件を整えるものであるが、光、空気、人の出入り等
々を、それぞれ個別に配慮して外界との交通をはかってゆく手続きをとるとす
れば、光を入れるつもりでも音が侵入してきてしまう。光の計画からすれば〈
ずれ〉が発生する。
⇒有孔体の単位は、矛盾を多分に内包した空間でしかありえなく、計画は
〈ずれ〉の総体となると言わざるをえない。
均質空間に対して差異をもつ空間を誘導しようとするとき、これに代替する空
間概念を明示できない状況にあって、方向性はひとつの有力な要因である。
[有孔体の単位の結合は]に対応して
空間単位から誘導される様々な交通は、それぞれの単位に新たな搾孔作業を発
生させ、なんらかの調整のあと、単位は相互に連結させることになる。この場
合の孔は、当然ながらふたつの領域間の閾となる制御装置をもつ。
ここで言う作用因子とは、人やもの、様々な環境的な要素やエネルギー。
こうして連結された単位からなるコンプレックスは、それ自体が新たな有孔体
の単位と同等になり、さらに複合化した結果としてつくられた建物全体もひと
つの単位とみることもできる。
⇒有孔体とは、生成された集合全体を示す概念となる。
しかし、この規定だけをみると、配列規則全体にわたっての言及は欠如
していることがわかる。この点が有孔体理論の欠点ともなっている。
有孔体がひとつの建築として自立的な存在として定位するためには、それぞれ
の孔の集合全体が、全体の空間構造あるいは環境の構造を表示するように計画
されていなければならないのであって、その意味においては、局所的な領域や
孔の計画は、機械的になされるのではなく、全体に対して予見的になされなく
てはならないのである。