


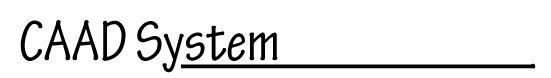
◇第3の様式
50年代からの住宅のシリーズは第1、第2の様式において日本建築の伝統を追求し、やがて意味と形におけるキューブを捉えるという軌跡を辿ってきた。篠原は70年代半ばを過ぎて日本建築のプロポーションを一気に捨て、日本的なるもの、日本の伝統に決別を告げようとしている。正方形は
45度の幾何学形態
となり、素材は始めは木造を用いていたが、次いで壁構造と移行し、ここではコンクリートの柱梁構造へ挑戦を試みる。構造の力、荒々しさがここでの建築の主題となっている。篠原は74年の秋にアフリカを訪れ、そこで人間の生の衝動を衝撃的に感じさせられた。この体験は後の作品の設計に大きな影響を与えたはずである。事実篠原はこの後住宅を設計するにあたって
“野生”
という語を多く用いている。
また、この頃には日本の空間に見られる強い抽象性や象徴性から生まれる具体的な確固たるものではなく、科学技術や都市,
カオス
など“不確かなもの”に興味を持ち始める。
意味の機械、
零度の機械
と言った言葉に見られる「“確かな構成”のなかにある“不確かな事象”」はこの後の主な設計コンセプトとなる。