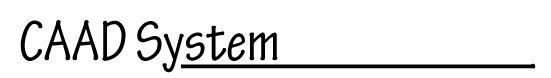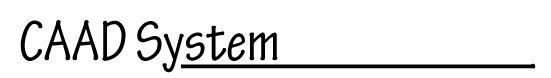

空間の象徴性についての美学的な見解は多数あるが、ここでは象徴性を全体的にとらえ
る一つの見解を説明する。その見解は「全中全の原理 all things are in all things
principle」と呼ばれる。この原理は必ずしも空間そのものについて展開されたわけで
はない。しかし、空間に即して理解することができる。古代ギリシアにおいてはアナク
サゴラスが、すべてのものはすべてのもののうちにあるという見解を提起した。彼の考
え方を現代の視点から解釈すれば、どのような事物をとってもそこから無限項目の性質
が抽出できるゆえに事物は同等であり、ふたつの事物がこの点に関して相包含する関係
をもつゆえに原理が成り立つとした。従って、アナクサゴラスの見解は象徴的というよ
り分析的傾向をもつ。ネオプラトニズムになると、非物質的なものにこの原理が適用さ
れる。例えば、プロクロスは「すべてのものはすべてのものの中に存在するが、自分に
ふさわしい存在形式をとってそれぞれのものの中に存在する」とする。ニコラス・クザ
ヌスはこの原理を、〈縮限 contractio〉という概念によって説明する。即ち(万物
を包括する宇宙の統一性である)宇宙の一性 universalis unitas essendiは、多様
pluralitasのうちに縮限されており、多性なしにはこの統一契機も存在しえないので
ある。彼によればこのような神的なことがらへの接近は、象徴によってのみ可能である。
全中全の原理は、ライプニッツに至って完成される。ライプニッツのモナドは、事象的
な点、いいかえればそれぞれの実体であるが、それらはそれぞれに〈宇宙の鏡〉であっ
て、そこに宇宙がうつし出されているのである。このような思考の系列が、住居のなか
の宇宙、都市のなかの世界といった象徴的表現の背景になっているし、また、具体的な
現がこうした思考を生みだしているのである。
こうした西欧の思考の系譜とは別に、日本中世の象徴の美がある。日本中世の仏教的な
象徴主義的傾向は、その起源を西欧の思考過程とは異にするものの、結果的には全中全
の原理と相似の原理を表現の領域に生みだした。坪庭、茶室などがその具体例である。
日本的な象徴主義の根源には、〈非ず非ず〉の超越的な論理形式がある。この論理形式
は絶対的、超越的なものの説明形式であり、古くはウパニシャッドの文献に見られ、仏
典にもみられる。次いで、日本中世の学問全体に大きな影響を与えた「摩訶止観」では、
この論理形式が論の展開の主軸となる。この論理形式の美学への適用は、仏教的修練と
芸術の表現行為とを同一視する歌論に現れ、次いで連歌論に受け継がれる。即ち非ず非
ずによってのみ示される絶対的な理念は、すべてであると同時にすべてでなく、またそ
うでなくもないものであるゆえ、象徴形式によってのみ表現可能であり、従って、どん
な小さなものにもすべてが表現可能となる。
このように、象徴性をめぐる空間概念として西欧と東洋の両域にわたり、類似したひと
つの原理が把握され、この原理のうえに様々な論議が展開された。
□象徴性を考慮しているもの