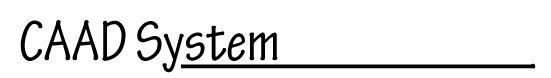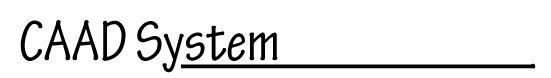

実在する空間は、概して、連続性をもつと考えられてきた。連続性は、空間がどこまで
可分であるかという観点から論じられる。非連続性を主張する見解として、レウキッポ
スとデモクリトスによる原始論的見解と空虚の存在の主張が挙げられる。「空虚がなけ
れば運動はありえない」と考え、その空虚 kenonは「離れてある」と考えた。こうし
た空間の非連続的な把握が明快になるのは、イスラムの神学カーラム Kalamにおいて
である。カーラムの学者たちは、神があらかじめすべての事象を決定しているという見
解を排除し、神はそのつど自然界における現象に意志を挿入しそれを決定すると考えた。
従って、まず時間は非連続的にとらえられる。事物の運動は時間的にみて非連続的な飛
躍 jumpの連続である。この実在する事物とは実体であり、原子と呼ばれる。原子に延
長はなく、点として位置を占める。原子と原子の間には空虚があり、空間はそれら非連
続的な空虚の集合である。原子は、この空虚のあいだをジャンプすることによって運動
する。また、原子が密に集合するとき、事物の形態が生じる。ヤンマーはこの空間を構
成する要素である空虚を、〈空間要素 space element〉と呼んでいる。また、カーラ
ムの考え方がライプニッツに影響を与えていることを指摘している。モナド即ち「実体
の原子」「形而上学的な点」は、離散的に構想される。しかし、ライプニッツはそれら
の点の配列に関しては言及しておらず、実体間の「交通」という関係性を記述するにと
どまる。従ってカーラムのような離散的な空間像はもたなかった。カーラムの空間像は、
純粋な意味での非連続論として希少価値をもっている。
建築においては、境界づけられた領域が頻繁に現れるため、空間は巨視的に連続的にと
らえられると同時に非連続的にもとらえられる。カーラムの空間像は特異に思われるが、
われわれは通常そうした空間把握をしていることに注意を払う必要がある。
□連続性を考慮しているもの