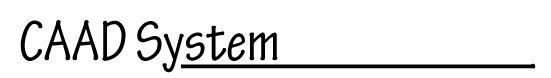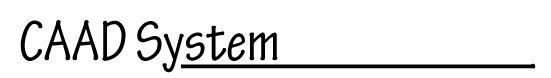

アリストテレスが、世界の唯一性を主張するのに対しデモクリトスは、世界は無数にあ
るとした。西欧やイスラム域においては神学のうえから、世界の唯一性が唱えられるの
が一般であったが、ルネサンスのころになると世界の多数性という考え方がブルーのに
よって提起される。この見解の差異は近代の特性を示すものであるが、それ以前にネオ
プラトニズムの哲学者たちによって、神の唯一性と現実の存在物の多様性との間を文脈
づけるための論理が提出されていた。それは一般に〈一と多〉の問題として知られてい
る。ネオプラトニズムが整えた〈一と多〉を説明するための論理ないし概念は、〈発出
あるいは流出 pro-hodos,emanation〉である。〈発出〉は絶対的な〈一〉から階層
的に漸次下位の世界が生成され、やがて現実世界が形成されるとする論理装置的な概念
であり、この考え方は後世に大きな影響を与えた。ルネサンス期以降、多様性の問題は
様々なかたちで論議される。ライプニッツは〈多〉はその事象性 la realiteを本当の
〈一〉、つまりモナド monadからのみとらえられるとし、それら多数のモナドの秩序
は〈予定調和 l'harmonie preetablie〉によってあらかじめ定まっているとする。
多様な諸性質、諸要素を統一する概念は、〈実体〉と呼ばれる。ライプニッツが予定調
和を説明したのも、実体概念においている。ロックは多様な様相を統一する契機を実体
に求めたが、何故に統一されるかは不可知であるとした。しかし、ロックはまた、複雑
な観念が〈関係〉によってもとらえられることを示していた。ロックにとって関係の本
質は「2つの事物を相互に関連させること、いいかえれば比較すること」である。多様
な要素のあいだの秩序が関係によってとらえられるという考えは、近代においてしだい
に有力になり、有機体論はそれを代表する考え方となる。また、現代のシステム理論な
どは、関係性によって多様なるものの秩序を把握しようとする代表的な理論である。
以上述べた多様性は、1つの原因によって秩序づけられる一元論的な枠組みのなかでの
多様性であるのに対して、もともと異質なる要素の同時存在を許容し、統一的な原理を
問わない多元論的な空間把握もみられる。インドにおけるヴェーダの時代の世界像がそ
の一例で、その伝統を継承して今日においてもいくつもの中心があり、異質な住居から
構成される領域などからなる〈混成系〉の集落の事例をみることができる。統一的な原
理を欠きながら異質な諸要素の同時存在を認めてゆこうとする態度は、西欧文化にも現
れアナーキズムの思想、シュールレアリズムの美学などにその例を見ることができる。
□多様性を考慮しているもの