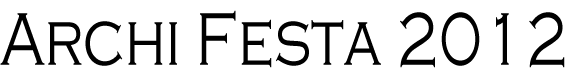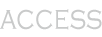建築学科/ 建築工学科/ 環境システム学科
■建築学科
| image | No | Name | subscription |
|---|---|---|---|
 |
J08002 | 天笠 絵里加 | 小学校の跡地にメディアセンターを計画する。新たな役割を与えることで土地の再生と地縁・地元愛の構築を図る。 |
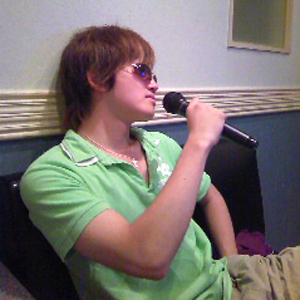 |
J08020 | 大和田 久徳 | 駅裏における公共的発展の可能性。 町田駅を例にとり、周囲の発達から取り残された駅裏の再開発を提案する。様々な行動が交わる場で、従来の駅の利便性とは違う価値の提供。 |
 |
J08022 | 岡本 章大 | 自転車と建築について考える。自転車は東京というスケールに合ったモビリティであると言える。普段駅毎に認識している町並みの風景を横断することで、今までとは違った東京の魅力を発見する。 |
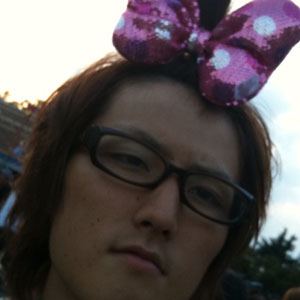 |
J08024 | 長田 大樹 | 都電が走り、未だに昔ながらの人間関係が残る下町—荒川区町屋。 この街の持つ問題を考察・解決し、再構築していく。 |
 |
J08025 | 小山 沢 | 「聖なる空虚」人々が集合するということ。一体の群れから立ち上るエネルギーは、未来への切なる祈りを乗せ、空へ放たれる。叫び、嘆き、呻きを受け止め新しい予感を共有する、そんな場所を日比谷に提案してみたい。 |
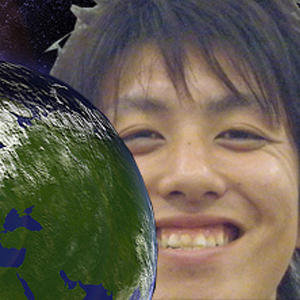 |
J08027 | 片山 豪 | ガソリンスタンドという場所。 都市インフラを支える影の功労者であるが、現在では減少の一方をたどっている。しかし、3.11以後、彼は主役として私たちの生活の起点となっていく。 |
 |
J08028 | 加藤 健司 | 自らの文化圏外において心理的シェルターとして機能する今日の国際標準化されたホテル。新しいルールによる要素の再構成によって、浅草で外国人と日本人のためにinternationalでregionalなホテルの再構築を図ります。 |
 |
J08033 | 菅野 成美 | 「自転車好きが集まる」現代における自転車問題を集合住宅という形で解く。そこで生まれる住民の活発な動きを表現する。 |
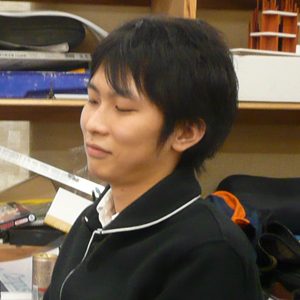 |
J08034 | 京兼 史泰 | 東京都大田区蒲田は町工場の街として有名であるが、それが羽田空港の国際化に伴って変わろうとしている。都市のdynamismから取り残されつつある町工場と無秩序に巨大化し、identityを失う街。 この2つが相互補完するように街を再編していきます。すると新しい都市空間が生まれる。 |
 |
J08039 | 黒川 舞花 | 今日の日本では、都市の人口集中や地方の過疎化が深刻化しています。 これらの唯一の対策が田舎での人との交流にあると私は感じています。 「緑・街・人を身近に感じる事の出来る交流居住施設」を計画し、 新たなライフスタイルを提案します。 |
 |
J08040 | 桑原 ゆかり | 独居老人・核家族世帯の増加の中、お互いがより安全で快適な暮らしを目指すため 多世代で暮らす居住空間を提案する。そしてここで発生する住民同士のコミュニティ が地域コミュニティにつながるものとなる。 |
 |
J08045 | 近藤 裕里 | 小学生の頃、学校の境界を飛び出してまち中を駆け回り、まちと1つになって遊んだ記憶。まちと一体化した小学校を提案する。 |
 |
J08046 | 郷 格 | 大震災以降、住まい方や共同体のあり方が考え直されている。 そこでわたしは都市に永住するための集落を計画する。 多くのインフラや施設の発展した都市でこそ新たな共同体の可能性があるのではないのだろうか。 |  |
J08047 | 後藤 健一郎 | 駅における滞留と流動について。駅は毎日多くの観光客と通勤・通学客が利用する。 |
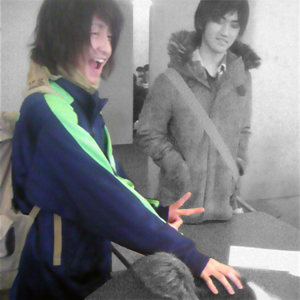 |
J08049 | 坂上 優 | 古典主義におけるパラディオの整形手法に新たに重心という整形手法を重ねる。 |
 |
J08055 | 佐藤 水紀 | 日常生活において、世代の異なる者たちの関わり合いが少なくなってきているように思う。とりわけ、子供と高齢者の接点を増やしたいと考えている。敷地は江東区南砂地区。小学校のある区画の特徴を活かし、双方が関わり合えるような新たな老人施設を提案する。 |
 |
J08061 | 庄司 健太郎 | Wall of dramaturgy. "壁"の再構築。 物理的壁として作用していた小田急線が、地下化される。そこに、"演劇の壁"を立ち上げる。 現在の下北沢の生態系を保持しつつ、演劇の街としての価値を生成する。 |
 |
J08067 | 菅原 晃 | 趣の街銀座…。この街も何度かの“再生”を行い、残された物に”路地”、そして失われた物に“水路”がある。これら2つの要素が新たな”にぎわいの場”を生み出すのではないか。未来の都市の”カタチ”を示す。 |
 |
J08073 | 田窪 真也 | 神楽坂花柳界発祥の背景には、行元寺境内に町屋のために存在していた路地空間の性質の読み替えがある。 経済的合理性のために場所・空間を商品として消費するのではなく、暮らしの中でそれらを読み替えていくことで、時代を超えて継承する。 |
 |
J08081 | 寺田 昂祐 | 現代の都市型集合住宅は住戸が密に積み上げられている。しかし、密な建築の内部は閉ざされている。 住戸と外部空間の割合を変化し、空間を共有し生活感がにじみ出る、新たなライフスタイルの都市型集合住宅を提案する。 |
 |
J08084 | 中川 達也 | 都市の中での建築の役割が居心地<経済性となっている現状に疑問を感じた。 都市と建築・建築と人・人とモノ。 両者の距離感を縮める建築。 |
 |
J08087 | 長野 大真 | 悪いイメージを押し付けられた街。これからの街を考える。 |
 |
J08090 | 西山 康史 | 経済合理主義によって構築された現代の都市に、旧用水路、河川、地勢などの歴史的、自然的与条件を再び浮かび上がらせ、既存の都市に重ね合わせる事により「仙台」を用いての今後の都市像の提案。 |
 |
J08112 | 宮原 健太 | 都市中央に圧縮された生活機能を解体し分散させ、建築内部から溢れた気配で街を覆う。無意識のうちに共存していたコミュニティを再確認できる都市ルールを表す建築によって街全体で“生活”という劇を創り上げる。 |
 |
J08113 | 森 瞳美 | 商業建築の再構築と、街の編集。 |
 |
J08116 | 森本 大悟 | 近年では日本においても外国人を見かける機会が増えている。 しかし、私たちは普段の暮らしの中で彼らの存在に目を向ける事は少ない。 外国人と日本人がどのように関わっていくべきかを日本語学校を軸として計画する。 |
 |
J08117 | 諸橋 俊 | 人は、怖いものを知りたがる。死という人生で最大の恐怖を必ず経験するにも関わらず、墓は塀に囲まれ、仏壇は減少している。無宗教化による合理化が進む葬送形式や葬送空間を再考し、日常で「死」を陰ながら感じる建築を提案する。。 |
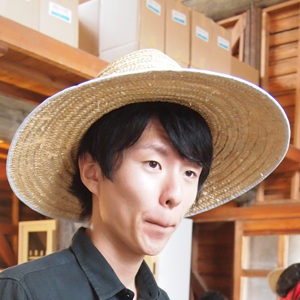 |
J08123 | 陸野 雅人 | 1枚の窓から始まる戸建て住宅集合の提案です。都市にはさまざまな景色や風景が溢れ、とても魅力的な表情を数多く持っています。住宅からそれらを感じ取れれば、都市に住む意味を見出せるのではないかと思いました。 |
 |
J07065 | 鈴木 雄哉 | 建築スケールと土木スケール。両者の間の建築を考える。 |
■建築工学科
| image | No | Name | subscription |
|---|---|---|---|
 |
K08005 | 安藤 光洋 | 都市の中に高層に積まれていく、閉ざされた住空間を見直し、人々の生活が都市と密接に関わる住み方を考える。都市と人の境界であるカベ再考する。カベを通して生活空間を再認識することで本当の豊かさに気づく。 |
 |
K08009 | 石崎 春奈 | 流れの早い都市の中で人々は単調な日々を送っている. そこで会社と自宅との間にもうひとつの居場所をつくる. 人々はその場所でさまざまな人と出会い, 社会や日常を普段とは違う視点から見つめ直す. たくさんの人が日々の通過点として利用する駅. そこに人が憩い,コミュニケーションを図る場を設計する. |
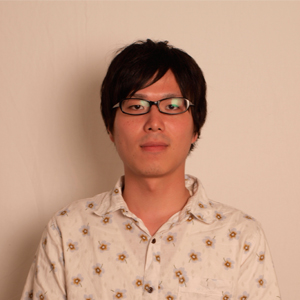 |
K08015 | 岩岡 岳 | コミュニケーションという人と人とをつなげる目で見ることのできない抽象的で曖昧な言葉をカタチとして表現し、都心にある団地の抱える問題を解決しつつ地域コミュニティを形成しやすい豊かな暮らしを実現できる集合住宅を提案する。 |
 |
K08040 | 亀田 昂甫 | 空港市場。2050年までに世界人口は現在よりも2-30億ほど増えると予想されている。それに対して日本人口は3000万ほど減少するだろうと言われている。今後、経済をはじめとして、あらゆる面においてグローバル化の動きが加速していくだろう。それは同時に、世界的な大移動が起こることを意味する。 |
 |
K08057 | 佐藤 春樹 | 都市での生活の中で子どもたちに違和感を感じる。住宅は内向きに閉じ、地域のコミュニティは衰退、学校は閉鎖的となっている都市の中でこの子どもたちの居場所はいったいどこにあるのだろうか。子どもと社会の新たな関係を考える。 |
 |
K08068 | 関矢 陽弘 | 21世紀は、価値のあるものをつくり、手入れをし、長く大切に使う、ストック型社会への転換が求められている。今設計では、東京湾全域を資源とみなし、東京湾の抱える環境問題に着目し建築で改善することを目的とする。 |
 |
K08081 | 内藤 正宏 | 今後起こる地震の多くが、都市を巻き込む。大量の仮設住宅が必要になる。しかし、都市にはその量を裁くほどの土地がない。そこで、“Backup city”を、都市に備えておく。通常時「職、住、遊」の“遊”として機能する。震災が起きると、都市の崩壊した場所から、人がやってくる。そして、“遊”は“住”に変わる。 |
 |
K08082 | 中山 裕太 | 大学が都市にプレゼンをしていかなければ都市の成長は停滞するだろう。ベイエリアにおける産業クラスターの生成をめざし、情報の生産地としてのハイブリッドユニバーシティーを提案する。 |
 |
K08084 | 奈雲 政人 | 東京を囲う巨大な現代博物館を提案する。 |
 |
K08095 | 東出 優子 | かけがいのない建築をつくりたい。 そこにしかない時間をつむぎあわせていくようなこと。 都市の近代化に置き忘れていった街の一画には、何百年ものあいだひとつの境界線が眠りつづけていた。 この境界線に新しい価値を見いだすことにより、この場所にしかない関係性を再構築する。 |
 |
K08099 | 藤井 千佳 | 建築の死も人間の死もより良い都市形成のための大事な要素ではないだろうか。生だけではなく死による都市の活性化を目指し、死ぬ火葬場とそれに伴い生まれる公園墓地を設計する。 |
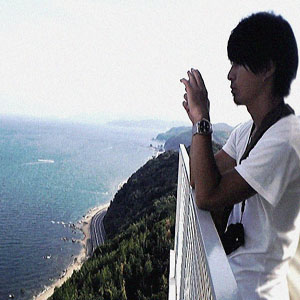 |
K08100 | 宮崎 侑也 | もうひとつの街。都市の魅力を引き出すような建築。 建築は地球にある限り、時間や環境や人や様々な影響を受けながら存在する。 そんなそこでしかない状況を受け入れてくれる場所をつくりたい。 現代の都市に残されたもうひとつの街は、固有の場所として新たな出会いを紡ぐ。 |
 |
K08107 | 古舘 慎太郎 | 暦、時間、星座、一年の周期。 これは全て空から得られた贈り物です。 しかし近年人間により浸食され、都心から星は姿を消しました。 それは現代においての空の在り方言えます。 そこで私は星の見えない天文施設を提案します。 |
 |
K08108 | 宮地 和明 | 住宅は生活の器となるものであるが、生活はその器からあふれ出している。これは、生活機能の外部化という現代の現象として現れている。この外部化されたものを含めて、住宅を再定義し、多様な空間、時間を表出させる。 |
 |
K08111 | 村松 沙綾 | 1つの構造体の発見。その構造体の可能性についてさぐる。いろいろなスケールや形態によって展開されていく。 現代の箱型建築のつめこまれたつまらない都市に何か象徴性を つくり人々の心に刻むものをつくる。 |
 |
K08112 | 文 由佳 | 長い時を経て そこには時代や種類の違うものが存在する 新しいアイデアは古いものを使うしかないのだ かつては威勢のよい工場地域が今は閑散としてしまっている。 工場とアトリエ。 そこには確かな技術とデザインが存在する。 再び、工場地域を浮かび上がらせる。 |
 |
K08115 | 山賀 悠 | この設計は、多面体から発展させた構造体によるタワーとドームで成り立つ環境保全システムの提案である。 この設計の最終目標は、タワーとドームという形態のかけ離れた二つの建築物によって生まれるシステムを模索し、それによって近年、世界各地で深刻な問題として挙げられる環境問題に、どのように建築的アプローチができるかを提示することである。 |
■環境システム学科
| image | No | Name | subscription |
|---|---|---|---|
 |
R08010 | 荒蒔 千加良 | 現代のひととまちのつながり方を設計する。 |
 |
R08038 | 榑沼 佑太 | ふるさとの長野の賑わいがなくなってきている。 長野五輪の頃の賑わいを取り戻したい。 そこで長野市中心市街地活性化の象徴となるものを計画する。 そして賑わいを長野に広めていく。 |
 |
R08062 | 津吹 有香 | ふ異なる国籍の人々が住む大久保地域に、自分たちを表現する場所をつくる。 生活というアートから、懐かしさとともに同じ小さな地域で住む人を知る |
 |
R08068 | 中村 仁美 | 「忘れものの大学」学歴社会、偏差値思考の世論に伴い教育はサービス化されてゆき、「大学」はもはや最高等教育機関としての威厳を失った。先の見えない教育方針に翻弄され、ゆとり世代と揶揄されてきた私達は、「大学」で何を学び、これからどんな社会を築くのだろう。私達は何か大切なことは忘れてはいないだろうか。 |
 |
R08083 | 松原 輝 | 港町横浜における魚文化の中心地の設計。商いを通じて漁師と、 地元の人や観光客が直接関われる場所となることを目指す。 |
 |
R08095 | 吉田 衣里 | どこにでもある駅から、そこにしかない駅をつくる |