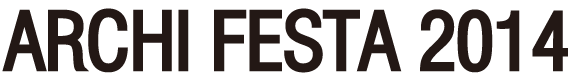建築学科/ 建築工学科/ 環境システム学科/ デザイン工学科
■建築学科
| image | No | Name | subscription |
|---|---|---|---|
 |
j10030 | 金丸 史歩 | 少子高齢化の進む現代社会において、日本各地で過疎化地域の再生活動が行われてきた。しかし、これらはすでに過疎化してからの対策にすぎなかった。今回の計画では、まだ過疎化はしていないが、将来過疎化が見込まれる地域を対象にし、過疎化に先手を打つ形で、地域の住人同士の交流や外部からの集客、内外の人々交流などを充実させるためのシステムや空間を提供することにより、農村地域の過疎化を防ぐ地域活性のしかけを提案する。 |
 |
j10088 | 長崎舞子 | 移り住む。生まれる期待と不安。今までの住処を捨て、新しい住処を求める。そのとき、人はなにを思い、期待し、不安を覚えるのか。 進化を求め、発展し続ける都心。取り残されていく郊外。そして、高齢者。固く護られたなかで過ごしながら、緩く紡がれていく「高齢者とともに移り住むまち」としての新しいまちのあり方を探る。 |
 |
j10091 | 西尾菜々香 | 今の日本には「最期の時」を待つだけの「待ち人」であふれている。2007年超高齢化社会に突入し、平均寿命は大幅にのびた。しかし新たに与えられたこの時間の使い道を私たちは知らない。 プライバシーという名の高い壁により社会との接点を失い、アイデンティティの迷走状態に至った高齢者に再びアイデンティティの再構築をはかり、日々生き甲斐をもちながら過ごせる集合住宅を提案する。 |
 |
j10094 | 花島将太 | 単身者の増加、核家族化のより、他の世代との交流が希薄になった。その傾向が強い都営住宅において多世暮らすためのプログラムと建築を提案する。集合住宅において現在、曖昧になっている「イエ」と「ヘヤ」を区別し、世代ごとの生活に変化を与え、外へ表出する。ひとつ屋根の下で多世代が暮らす。それはただみんなで仲良く暮らすことではない。互いに気配を感じあいながら、現代では生まれにくい多世代での交流を目指す。 |
 |
j10097 | 原田稜 | 現在の葬送空間は、日常から切り離されている。何気ない風景の中に突如現れ、’死’に直面する。 空気感や目に見える物が劇的に変化する一方で、私たちは人の’死’を簡単に受け入れるべきではない。大切な人との別れの為には時間をかけて様々な思いや感情に向かうべきではないだろうか。 自然を取り込み、自然現象をより顕著に感じさせる建築的操作を加える事で、最期の別れの場にふさわしい葬送を再構築する。 |
 |
j10110 | 宮島夏実 | 近年、商店街の人と街の絆が商店街の寂れとともに失われている。この提案は学生一人暮らしの生活を商店街の暮らしに組み込み、互のデメリットを互のメリットで 補う。提案が進むにつれ建築物や生活のツナガリが濃くなり、「学生」「商店街」「地域」の関わりを導く。 |
 |
j10130 | 若佐谷唯 | ”あんずますぃ”とは心地よいなどを意味する青森の方言である。地元民・観光客・ビジネスマンなど様々な人が、新青森の地を”あずましい”と感じることのできる都市・建築を提案する。東西と南北の各幹線道路の性質に対応させた都市の施設の再配分[都市]と、青森・弘前・五所川原の3つのねぶたの展示施設および市民センターの複合施設[建築]を提案する。 |
 |
j09085 | 芳賀言太郎 | 祈りとは、目に見えなくとも確かに存在するものに対する呼びかけであり、耳に聞こえないものからの呼びかけに耳を澄ませることである。私は教会の可能性を信じている。外界の喧噪から切り離され、天に向かって開かれた空間として、教会もまたすべての人に開かれるべきである。その時、教会の美しさもまた人々への祈りへの招きとなるに違いない。巡礼の地で出会った光と祈りの空間を再考し、未来に残る恒久的な教会を設計する。 |
 |
j10035 | 川島優太 | 凝り固まった考えや思い込みのことを固定概念という。現代でも悪い意味でこの言葉は残っている。 墨田区東墨田にはこの言葉によって今まで苦しめられてきた地域がある。差別部落。未だにその言葉を口にする者も少なくない。そんな地域を固定概念から解放し、新しいイメージで構築する方法を探る。 学びをテーマとして地域に散らばったところを提案する。 |
 |
j10019 | 内田健太 | 静かで賑やかで、ゆっくりで速くて、小さくて大きくて、いっぱいあってなにもない。私は皇居外苑前広場に流れる時間と空気に魅力を感じ、それを建築化したいと思った。とても奇妙で魅力的な体験と風景を分析し建築化すると、そこには空虚な空気を纏った広場の様な建築が生まれた。様々なモノで埋め尽くされ、余地をなくした東京に生まれた新たなvoid。そこには、誰もが目的なく気軽に集い、憩える広場の様な複合施設が現れる。 |
 |
j10059 | 鈴木愛子 | サービスエリアと町との関係を再考し、グローバリゼーションとローカリゼーションがより良い関係を築いていくための建築。敷地である静岡市由比に集中する動線を整理し、インフラが町を分断している問題を解決する。また、産業発展にふさわしい海辺に人の流れを作りだし、街の中心となるサービスエリアを提案する。 |
 |
j10069 | 竹内朝子 | 雨をしのぐことに始まった建築は、風を防ぐ壁をたて夏にはクーラーを夜には明かりを灯し、太古から今まで絶えず進化してきた。これは進歩に他ならないが、同時に人は自然の流れに逆らってきたようにも見える。人の生活はだんだんと「不自然」になりつつある。世界の集落にはヴァナキュラーな建築のように、環境に寄り沿って自然に暮らせないか。都市という環境において、動物として住む。そこにかつてあった人への愛着を再生したい。 |
 |
j10080 | 富所賢斗 | 都心部ではなるべく多くの容積を獲得するため、街区開発などでかつては住宅地であったところにも中~高層建築群が密集するように建て込んでいる。 外部空間はビルからこぼれ落ちた谷底のようで底からの空は細く遠く、都市の日常では本来の大きな空を経験することができない。 街区ブロック全体の屋根形状をスリバチ状に規制することで山間の盆地のような空に開いた新たな「都市=自然」をつくる。 |  |
j10095 | 早坂いづみ | 神奈川県横須賀市。比較的、日本のなかでも米軍基地と上手く付き合ってきた見えたまちであるが、実際には、日米が積極的に融合して存在していたわけではなく、互の顔が見えない相手が隣り合わせで存在している。 土地への敬意を払い、現代の日米関係の修復・治療を、建築を用いて施す。日本とアメリカ、それぞれの小学校を設計する。 米軍基地(Base)のゲートの前で、その先にある異国への風景に思いを馳せてみる。 |
 |
j10096 | 早船雄太 | 東京都青山に建つこどもの城。今回は2017年に閉館するこどもの城の建て替えを行う。経済主義の一元的な社会の流れで生まれた一元的なこどもの城の閉館を契機に、現在の多元的な社会の中で持続しうるような多元的なこどもの城をつくっていく。 敷地の見えないコンターを読み取り、それに呼応するグラデーショナルな都市の丘を形成する。 |
 |
j10098 | 平井開汰朗 | 高齢化が進む都市において、ホスピスを設計する。自分の余命がわかってからの時間の心理的感覚をジャネーの法則から反転的に導き出し、設計手法の一つとする。末期に近づくにつれ、患者の認識解像度が高まり、微差を認識するようになる。飯田橋にある都市が持つ軸から生成したグリッドを源泉としてその微差の証拠とする。その内側の空間は、患者が最後に1人になれる場所であり、彼の人生の走馬灯空間となる。 |
 |
j10114 | 森岡歩美 | インターネットの普及によりいつでもどこでも社会へアクセスできる時代。人々は現実世界で対話をせずとも生活できてしまい、液晶画面の向こう側をパブリック空間なるものとして生活している。 廃止となる田町車両基地。高密度な都市に生まれた大きな空き地に、都心部から失われてくパブリック空間を創出する。線路と線路の間のリニアなスペースに連なる建築群が、現在の風景を残しながらも豊かなパブリック空間を形成していく。 |
 |
j10115 | 森田千尋 | 結婚するということは、家を持つということにほとんど等しい。 そして、これから長い時間をともにゆく2人の門出はとても大切なものであるはずだ。それにも関わらず、今日の結婚式場では、1時間おきに何組もの永遠が誓われ、さらにこれから続いていく長い2人の生活とは乖離してしまっている。2人の生活をともにつくっていけるような住宅を提案する。 |
 |
j10117 | 守屋真一 | 20世紀までは「どれだけ情報を得られるか」が価値であった。翻って情報化が進んだ今、「情報をどれだけ制御できるか」が価値になる。都市の中で情報を制御している空間として劇場(シアター)がある。コンテンツを享受することに特化したこの空間は都市の中で「情報とうまくつきあう」ための空間となり得る可能性を秘めている。衰退する映画館を軸にした複合文化施設を東京にできた”1,132mの余白”に提案する。 |
 |
j10026 | 柏崎壮太 | 都市の負の遺産となりつつある交通インフラは様々な問題を抱え、今日も都市の中で息づいている。そんな土木構造物と建築の新しい関わり方の提案をする。交通インフラの周りの建築ヴォリュームをインフラ側に寄せて積層させる。電車、車の騒音源からの距離でゾーニングを行い、人々とインフラの関係を良好に保つことを狙う。 |
 |
j10004 | 荒武優希 | 都市での暮らしが豊かになり郊外居住の価値が失われつつある現在、従来通りの無個性な郊外開発は更新期を迎えたといえる。ライフスタイルの多様化も相俟って住宅の供給方法も同時に更新期を迎えているといえる。地域の魅力を建築によって顕在化し地域に個性を生み出す共同体を提案する。 |
 |
j10008 | 飯山悟史 | 大架構の建築の中に発電所を計画し、公共的プログラムを上部から吊ること、傾斜地を利用することで断面的に両者の関係を構築する。エネルギー工場を見える化することで、人々の意識を変える啓蒙施設となるとともに、価値観が多様化するこの現代社会において小規模の地域社会をまとめあげる核となる建築である。 |
 |
j10021 | 梅津章一 | ニュータウン—かつて日本の住まいを守ってきた郊外のまち—しかし現代では都心に高層マンションが次々に建設されていき、さらに時間と共に家族形態が変わる昨今。郊外に住んでいる多く若者は都内に移り住んでいく。残されたのは緑に囲まれた老朽化した建物、まちに住む老齢化していく初入居時に住んでいた若い夫婦。私はかつて開発されたニュータウンをもう一度まちとして再生させる提案を行う。 |
 |
j10027 | 門井慎之介 | 私の原風景は小学校の通学路である。変わりゆくまち並みは複雑な風景を持ちうる。この風景はかつての私に豊かな経験を与えた。今、この複雑な風景が消えようとしている所がある。千葉県流山おおたかの森。「近さ=価値」現代の都市計画の基本概念により均質化したまち並みを造形している。この基本概念を「豊かさ=価値」に変える。進む郊外の都市計画に見える風景の再定義を行った時に人はどのような豊かな経験を得るのだろうか。 |
 |
j10039 | 岸毅明 | 東京の骨格である鉄道のネットワーク。結節点として点在する駅。それらは漠然とした東京像にメリハリを付ける可能性を秘めている。ここでは地下駅とそれが影響する駅前空間を対象とし、地下と地上の連絡の改善、駅と街の関係を濃密にすることを目指す。地下に街の中心があることは決してネガティブな状況ではない。それを活かした結節点を可視化する。 |
 |
j10057 | 塩飽紘彰 | 身近なものほど本来の魅力には気づきにくいものである。例えば活気を失いつつある地方の町においては、日常生活そのものが惰性的となり、場所の持つ固有性は人々の意識から消えてしまう。それは人と町と社会とがますます切り離されていく要因になりかねない。岡山県笠岡市。瀬戸内に面したこの町は歴史的な背景からも街が分断されてしまっている。本来の価値を見直し、再び町を結節させる”まち”をつくっていく。 |
 |
j10058 | 城代晃成 | これは「敷地」を超えた提案である。建築と土木が接近融合すれば、もっと豊かな風景ができるのではないか。限界集落化が進む長崎の斜面地におけるアクセシビリティの向上と持続可能性のあるプロセスのデザインを追求した。目的達成のプロセスを「編集」することでコラボレーションを生み、大きな風景を長崎の地勢に耳を澄まして再構成してゆく。 |
 |
j10060 | 鈴木海 | 街の魅力や風土が時代や社会の変化によって見えにくくなっている場所が多く存在する。そうした場所に対して建築はその場所の魅力や風土を顕在化することが出来る手段の一つである。自身の出身である石垣島を対象敷地にとり、島で起きている居住地の問題に対して新しい住まい方の提案をかつての集落を参照しながら行ってゆく。その背景を踏まえ住民と来訪者が共に生活できる居住の場を構築していく。 |
 |
j10065 | 高木理菜 | 本と人とが豊かに関わることのできる図書×保育園の提案。こどもとおとな。人々と自然。本がつなぐ様々なものの関係性を設計します。それは、長い長い人生においてはじめて本と出会う保育園。人生のはじまりの場所であり、何度でも帰れる図書館。 |
 |
j10068 | 滝澤美菜 | 地方がどんどん都市化され、街の個性がなくなってしまった。多くの都市の市役所は役割が増えたために郊外へと移転。そんな中、私の地元草加市は今も街の中心地にある。庁舎とその前通りである旧日光街道を一つの空間として捉え、役所機能を分散させていく。昨日が分散されることで通りが待合空間となり、人が溢れ交流が生まれ街と人が繋がっていく。 |
 |
j10108 | 松本文也 | あなたは「寺」に対してどのようなイメージをもっているだろうか。 近代化による都市開発などで、地域における寺の存在意義はうすくなっている。かつての寺が有していた機能等を見直し教育の拠点として寺のポテンシャルを再構築していく。寺と建築が未来の日本のまちづくりに対して関わる新たな可能性を導き、地域におけるモデルケースとして建築を提案する。 |
 |
j10003 | 荒木優太 | 団地は様々な慢性的な問題を抱えて生きている。その問題を解決しようとするのではなくそれを生活の一部に組み込む設計を行う。住人に合わせた生活や住人や他の地域の人が徐々にその生活に魅力を見いだしていく団地を提案する。団地に人のための空間を作る。 |
 |
j10056 | 白木達也 | 現代の子供たちは生まれた時から画面の中の世界に縛られている。ゲームもテレビもスマホモ便利で誰もが持っているがその便利さ故に失ってしまっているものもある。ゲームよりも面白いものがそこら中に転がっている、そんなことを子供たちに思ってもらえるような建築をつくりたい。 |
 |
j10125 | 横田裕 | 歴史的な影響から孤立化してしまったまちにかつての様子を取り戻してもらいたい。負の遺産・まちを閉ざす原因を観察し、そこで見えてきたものはまちを囲んでいる壁、運河と寂しそうなまちの表情である。この3つの要素を組み合わせることで再び元気なまちになることを提案する。 |
 |
j10127 | 吉田早織 | “更築”‥土地・建築・生活の共有を通じ自らの手で行う再構築。 少子高齢化に伴うようにして人々の繋がりは細分化され、また同じく細分化された土地・私有地がそれを助長している。この細分化された人・土地のありかたを建築が定義することで、そのできることの可能性をはかる。 |
■建築工学科
| image | No | Name | subscription |
|---|---|---|---|
 |
k10002 | 青柳野衣 | 2013年6月22日、富士山が世界文化遺産に登録された。しかし、富士山周辺には、どこにでもあるような観光施設が立ち並び、単なる「観光商品」としてのみ扱われている。観光資源としてしか富士山を捉えておらず、文化そのものが観光に反映されていないのではないだろうか。 文化遺産としての富士山を十分に享受できる観光、つまり自然、観光客、住民、3つの共生を図る場所を計画し、その場所にしかない観光のあり方を提案する。 |
 |
k10004 | 東拓哉 | 人と人の関わりが薄れていく今日、様々な人が関わり合い、地域全体で子供を育てていく、これまでとは異なる「教育」の環境が必要である。それには、学校建築以外で行われる「社会教育」の場が必要である。敷地は、東京都足立区千住仲町の木造密集市街地。敷地に存在する路地を再構築し、集合住宅と公共施設を複合化することで、社会教育の場を提案する。 |
 |
k10012 | 伊藤誠人 | 小学校に隣接する住宅地の遊休化した居室を小学校の敷地と一体化させ、街の中核を担う市民農園、自治会館、商店、福祉施設を複合化し計画していく。 人口減少期の公共施設の在り方と小学校の室空間の在り方、避難施設としての発災時の柔軟な利用に関する提案。 |
 |
k10023 | 太田浩樹 | 東日本大震災を契機とし、我々は今エネルギー問題などを見据えた大規模な社会システムの改革を必要としている。 「適応する建築」 適応とは、生物が環境に応じて形態や生理的な性質、習性などを長年月の間に適するように変化させる現象である。 この建築は「成長のための節」を与えることで単一空間が干渉し合い、都市の要素を内包して成長する。変化に富んだ建築は、多様で不調和な要素の動的均衡の状態として環境に絶えず適応していくのだ。 |
 |
k10046 | 小林多恵 | オンラインショップが一般化し、ショールーミングという、店舗を消費の場として捉えないような考え方が増加している。消費活動が目に見えに場所で行われることで、購買と都市の関係性が薄れてきているのではないだろうか。 そこで、オンラインショップとは逆のメリットをもつ百貨店の形態を利用した商店街、つまり「百貨街」としての建築を提案する。百貨街は人々が都市の中を回遊する場となり、また、多様な購買に触れることができる場となる。 百貨街は都市と購買をより密な関係にし、多様な購買を生み出す。 |
 |
k10052 | 宍戸日菜子 | 塀によって都市から隔絶された箱、刑務所。敷地に3つの生v活圏を形成し、刑期に従って生活の場を移していく。その中ではボロノイ分割を用いた領域形成を行い、管理された中で選択の自由が与えられ、大屋根によって内外はつなげられていく。自らの犯した罪を償う場所としてだけでなく、社会との関わり方を変化させていき、再起のための刑務所を提案する。 |
 |
k10094 | 堀口拓 | 用途を失った河川はまちも人も見向きをせず、境界として扱われ、淘汰された場所として時を刻むことを忘れてしまった。 |
 |
k10100 | 森島英貴 | 用途を失った河川はまちも人も見向きをせず、境界として扱われ、淘汰された場所として時を刻むことを忘れてしまった。 |
 |
k10115 | 若林拓哉 | “国民と国家を繋ぐ建築”の提案。政治に関心を向けずとも過ごすことが出来る日本。複雑多様化した現代社会と乖離した時代錯誤の現国会議事堂を、来るべき日本の将来像に適合し得る、国民のための新たな象徴として再建する。 権力から解放された空虚な中心は、多様さを受け止め、すべてを繋ぐ。今ここに、数百年続く”希望としても象徴”が建つ。 |
 |
K10087 | 東佳苗 | 時代と共に変化し続けている東京。新しい建築物が増え続ける一方、その影にはホームレスが必ず存在する。ホームレスは社会から隠れ、社会はホームレスに嫌悪感を抱いている。このホームレスに可能性を見つけ、社会に受け入れられるためのプログラムと空間を形成する。 ホームレスに価値を与え、社会に貢献することによって、受け入れられることを目指す。 |
 |
k10001 | 相宮裕香 | 東洋一の歓楽街と呼ばれる歌舞伎町。ここで子育てをする親の中には、指導されることに怯え、福祉の支援にも近づかない社会から逃げる親たちもいる。彼らは経済的にも精神的にも不安定になり、育児放棄へとつながってしまう。彼らに必要なのは支援ではなく仲間なのではないだろうか。そこで、家族を超えた子育てを行える集合住宅を提案する。 |
 |
K10044 | 小林宏至 | 来間島は少子高齢化で人口流出が続き、集落が縮小しつつある。島には、この島で培ってきた農業の知識や生活の知恵を教えたいと考える人達がいる。一方、島外には、定住に必要な生活の手段、農業の知識を知りたい人達がいる両者をつなげる必要があり、この来間島で知識を伝達する空間を提案する。 |
 |
K10102 | 柳田椋太 | 宮崎県の山間部に位置する椎葉村。椎葉神楽や焼畑など多くの伝達文化を今に受け継いでいる。それらが後世にも受け継がれていく方法を建築的手法を用いて提案する。 |
 |
K10021 | 江森湖輝 | 本計画の要旨は次の2点である.①近代インフラの更新と継承を試みること。②空間における公共性を再考すること。これらを考察する為に、それぞれにおいて《新しい国土》と「《途上の地点》の風景」という概念を用いることで、現代的な建築法の一つのモデルを考えてみる. 本計画はそれらの実現の為の試論である。 |
 |
k10029 | 奥野耀亮 | 都市計画におけるひとつの問題である、アンとガワの関係。ガワとは道路に接している場所であり、アンとは道路に接していない場所を指す。アンは、建築基準法にある接道義務を果たしていないため、建て替えを許されず、建物は劣化の一途をたどるのみである。そのような場所に於いて、現在とられている対策は、現状維持か再開発である。そのどちらもが、アンという環境が生き残るものではない。本計画では、都市においてアンが生き残るための積極的な方法、つまりは、アンとガワの良好な計画を模索していく。 |
 |
K10048 | 吾川綾香 | 現在、東京を中心とする東京都市圏には日本の人口の約3割にあたる3724万人もの人が住んでいる。しかしながら、昨今問題になるのは、人間関係のヒートアイランド化に対処すべく、東京の被緑地率をさらに上げることを目的とする。高層ビルの増加により外部での緑化が厳しい中、内部から緑化をきっかけに人と人を繋げ、街と街を繋げる複合施設を提案する。既存の人の流れと新たに設計する動線に基づいてに渦の形をモデルに施設に人々が集まるような建築を追求する。希薄化や孤独死といった「孤」による障害ばかりだ。なぜ世界最大数の人数が集まっていながら、そのようなことが問題になるのだろう。 上記の問題が起きる要因の1つに、団地やマンションの入居世帯の偏りがあることが挙げられる。 今こそ都市には、持続可能な関係性を保つ場所としての”OASIS”が必要だ。 |
 |
k10063 | 竹中亮善 | ヒートアイランド化に対処すべく、東京の被緑地率をさらに上げることを目的とする。高層ビルの増加により外部での緑化が厳しい中、内部から緑化をきっかけに人と人を繋げ、街と街を繋げる複合施設を提案する。既存の人の流れと新たに設計する動線に基づいてに渦の形をモデルに施設に人々が集まるような建築を追求する。 |
 |
k10077 | 中村達也 | 「工業団地(インダストリアルパーク)」。それは、都市ひいては国家が近代化を果たすためのマストアイテムであった。しかし、近代化の役目を終えた工業団地は、産業の空洞化によって大規模なスラム化と化す。本計画は、都市のなかの巨大な空洞になりつつある工業団地を、21世紀の産業構造にフィットしたシステムへと再編することを目指す。 |
 |
k10111 | 吉澤芙美香 | かつては強い公共性をもち、まちの拠点であったはずの駅の多くは現在、消費空間に覆われ肥大化し、均質化しつつある。しかしここで、電車がやってくる駅それぞれに、まち特有のリズムが刻まれていることに気が付いた。駅にまつわるリズムを契機とし、まちの文化によってかたちづくられる「駅」を設計する。 |
■環境システム学科
| image | No | Name | subscription |
|---|---|---|---|
 |
n09012 | 井上裕基 | 精神病院が成立する場の特性として境界性がある。精神病院は以前、交易の地や、墓地の付近に建てられていた。交易の地は異邦人同士が出会う場であり、墓地は生と死。いずれもその場所柄には境界性が封印せれた板。精神疾患の医療の場には、「正常」側の治療者と、「異常」側の患者の両者が介在し、一種の境界性を帯びた場であると言える。選定した敷地は、高地と低地に挟まれた斜面であり、一種の境界の地であると考える。 自然の地形であり斜面を人工的に作り替え、境界としての精神病院を露出させる。 |
 |
r10092 | 森晃彦 | モータリゼーションが到来する以前は、道路は『みち』であり、都市の居間となり、遊び場となり、さまざまな人生のドラマが演じられる舞台となる多義的な空間であった。モータリゼーションによって希薄になった本来の『みち』の機能を新たな形で人々に感じさせる空間を創り出す。 |
 |
r10026 | 大場瑞姫 | 近年、商業施設や鉄道の駅内の空間づくりが充実し、人々の生活を豊かにしていく一方で、地下鉄と繋がる迷路のような複雑な地下空間は殺風景で代わり映えのない通路が続く。 地上と切断された空間に地上との関係を持たせることで人と街を近づける「チカミチ」になる。 |
 |
r10034 | 片桐陵吾 | 私も含め日本人には気に魅力や愛着を持つ気持ちがあるはずである。人は、木を利用するだけでなく育てることも始めた。それが「里山」である。かつては持続的生産の可能な木を建築に用いてきたのだが、歴史の流れとともに里山の必要性が薄れ、減少の一途を辿っている。交流拠点となることで地域の活性化を誘発する価値の環境を目指す。新たな職を生成することで人間の営みにおける知の環境を創出する。 |
 |
r10047 | 佐藤友香 | 治水技術が発達する前、広がる東京低地帯では水の恩恵を受けながらも時には被害を受け、人の繋がりの中で戦い、共存してきた。 私たちは今、水の環境をあらためて知り、その豊かな治水環境で地域と知り合う「知水事業」を行い、失われた水への関心と人々の間のつながりを取り戻す必要がある。管理されていた治水空間を地域に開放するための「入り口」を設計する。 |
 |
r10062 | 中野雄貴 | 江戸時代に外来者の交通動脈として主要な役割を果たした深谷市中山道沿いの宿場町。昭和期には宿場跡地が商店街として中心市街地を支えてきた。しかし現在、商店街の衰退、空地化が問題となっている。この空洞化した街の裏側に新たな連続性と回遊性を与え、そこに地域の「家」をつくることで、第三の場としてまちの再生を計画する。 |
 |
r10067 | 橋口拡昌 | 東京都千代田区と中央区の堺に位置する日本橋川は、かつて物流や交流の中心として栄えていた。自動車交通の発達による区画整備から都市の裏側へと隠された日本橋川は、高速道路の高架が架けられ、まちを断絶する境界へと変化した。負の存在として認識される高架と日本橋川が作り出す環境に新たな価値を見い出し、生かすことで、断絶されていた人とまち、まちとまちの関係を再構築する。 |
 |
r10090 | 牟田万里奈 | 下町と都市を繋ぐ、都電荒川線の停留場(ターミナル)を提案する。対象地は、都電荒川線沿線につづく三ノ輪橋商店街。停留場を中心とし、商店街に新たなモビリティを生み出すことで、下町の「商い」を再編し、人々の生活を活性化するノードとなる空間をデザインする。 |
■デザイン工学科
| image | No | Name | subscription |
|---|---|---|---|
 |
y10039 | 松浦和正 | 少子高齢化や人口の減少が進み始めている中、集合住宅において新たな集合の方法を提案し、集まって住むことへの意味を再認識させる。在宅勤務者を想定しながら、適応する空間をつくりだし、フレキシブルな住戸プランを形式することや各住戸の外部に対する開き方を考え直すことで、居住空間の多様性や地域との繋がりが生まれる。 |
 |
y10030 | 永井綾香 | 「ゆるやかにつながる境界」をコンセプトに江東区清澄白河区域に2020年東京オリンピックに向けた集客施設A清澄庭園店舗向住宅、B水辺、C公園整備に分けて計画する。A清澄庭園店舗向住宅を中心建物とし、路地、スリット、既存増築部の拡張、庭園とのgiveandtake等境界をずらす。地域の特色を活かし、街全体が緩やかに文化的な空間となることを目指す。 |
 |
y10021 | 関聡 | 増え続ける利用頻度の低いスタジアムのコンバージョンを行い、今後の活用方を提案する。スタンドの架構を活かした大空間のある図書館や客席の斜面を活かした農園、また公園全体の緑を感じられるランニングコースを計画し、地域に開かれた新たな交流の場を提案する。 |
 |
y10010 | 奥源大 | 自然知覚力を高めるための水空間とそれを内包する建築の提案。 現代社会における当たり前を享受し続けたことで自然とのリアルで一体的な感覚が希薄になってまった日本人は古来、受容的かつ忍従的な自然観を持ち、豊かな水の文化を育んできた。東京近郊の行楽地である高尾山にその自然観を確認するための場所を考える。 |
 |
y10019 | 島田亜沙美 | 道路と呼べない程細い道に囲まれた木造密集市街地を、高低差を活かし動線や視線をデザインする。 耐火壁をつくることによって木造住宅の災害時の危険性にも考慮し、プライバシーを守りながら、路地に残るコミュニティを維持する。 |
 |
y10041 | 三田佳祐 | 本設計ではノマドのためのワーキングスペースを提案する。現在、働き方も多様化しオフィスを持たないノマドワーカと呼ばれる人たちも出てきた。今後そのような人たちの受け皿としての働くスペースが必要になってくる。多種多様なモノが集まる秋葉原において計画したが、今後広域に点在ネットワーク化してくことでより有意義なものになると考えられる。 |
 |
y10005 | 池田七瀬 | 東京という巨大都心の中心、四ツ谷には昔から変わらぬ風景と都市の変化の名残がレイヤーとなって刻み込まれている。本提案では江戸時代から残るこの空間に新たな歴史の一部として駅空間を挿入しまた一つの新しい歴史の層としてこの地に刻まれる。 |
 |
y10006 | 市川瑠美 | 地方都市の全蓋式アーケードを持つ駅前商店街を対象とし、アーケードの空間資源を利用したこども園及び多世代交流施設の提案を行う。子供たちは施設の中だけではなく商店街の中を駆け回りながら様々なことを学び、時間を持て余した定年後の高齢者がこども園の先生となる。こども・高齢者・親・買い物客・学生など様々な年代の交流で商店街の活気を維持させる。 |
 |
y10026 | 露崎裕也 | 近年、少子化や過疎化などが原因で廃校が増加している。学校は誰もが慣れ親しんだ空間であり、思い出の多い空間である。今回の提案では中山間地域における廃校を体験型の宿泊施設にコンバージョンした。地域住民と観光客がコンタクトをとれるような空間として再生できればと考え設計を行った。 |
 |
y10028 | 中川望 | 深刻な人口減少という問題を抱えながらも”自転車”という地域資源を生かしたまちづくりに取り組んでいる島根県益田市。ここに全国300万人のサイクリストが注目し自転車に集中できる空間を提案する。敷地は傾斜のある湖の畔。石見の地場産業である石州瓦と緩やかな自転車動線が新しい湖景観を作り出す。 |
 |
y10036 | 本多由香利 | 私の祖父の実家の神社境内の手前にある住宅、倉庫、蔵をコンバージョンし外国人バックパッカーの宿泊施設にする。地形の段差を利用して目線と目線で繋ぎ、バックパッカー、地域の人、神社の参拝に来た人との交流の場になる。 住宅に地下をつくり、そこから地形の交流の場に繋がっていく。 |
 |
y10037 | 眞﨑琢也 | 世界の主要都市では古くから水辺空間を重視し、魅力的な空間を創出している。東京都心の水辺空間は水運の衰退以降は裏に扱われ、人々を惹き付けるに至っていない。本研究はそのような水辺空間で鍼灸の建物や空間が交じり合う京浜運河沿い街区を事例に魅力的な水辺利用の提案を行う。 |
 |
y10038 | 真砂慎太郎 | 14棟の独立した建物ユニットをスラブでつなぎ、全ての個室から水辺を感じられる配置とした。1階部分は地域にも開放し、2階より上は住居者専用とし3層ごとにコモンリビング・キッチン・ダイニングを配置し、各階にはコモンスペースを点在させた。 |