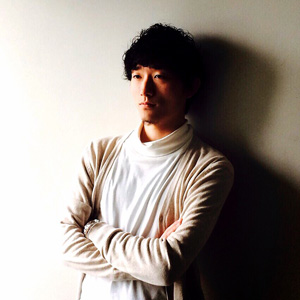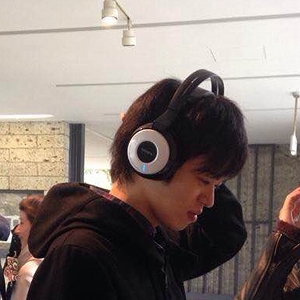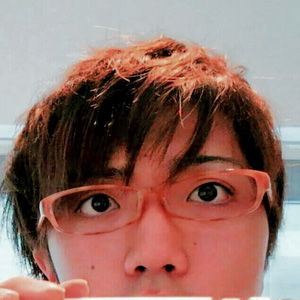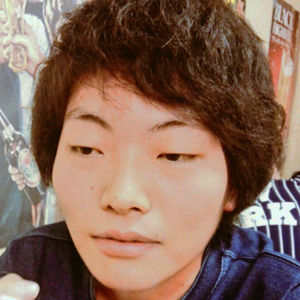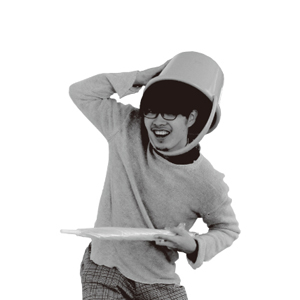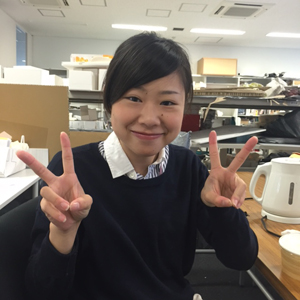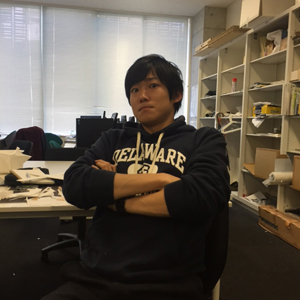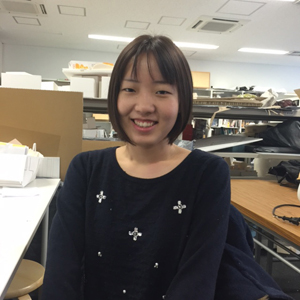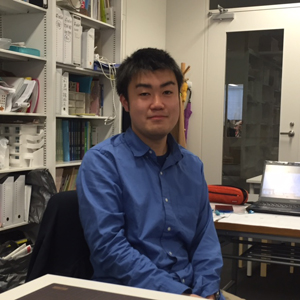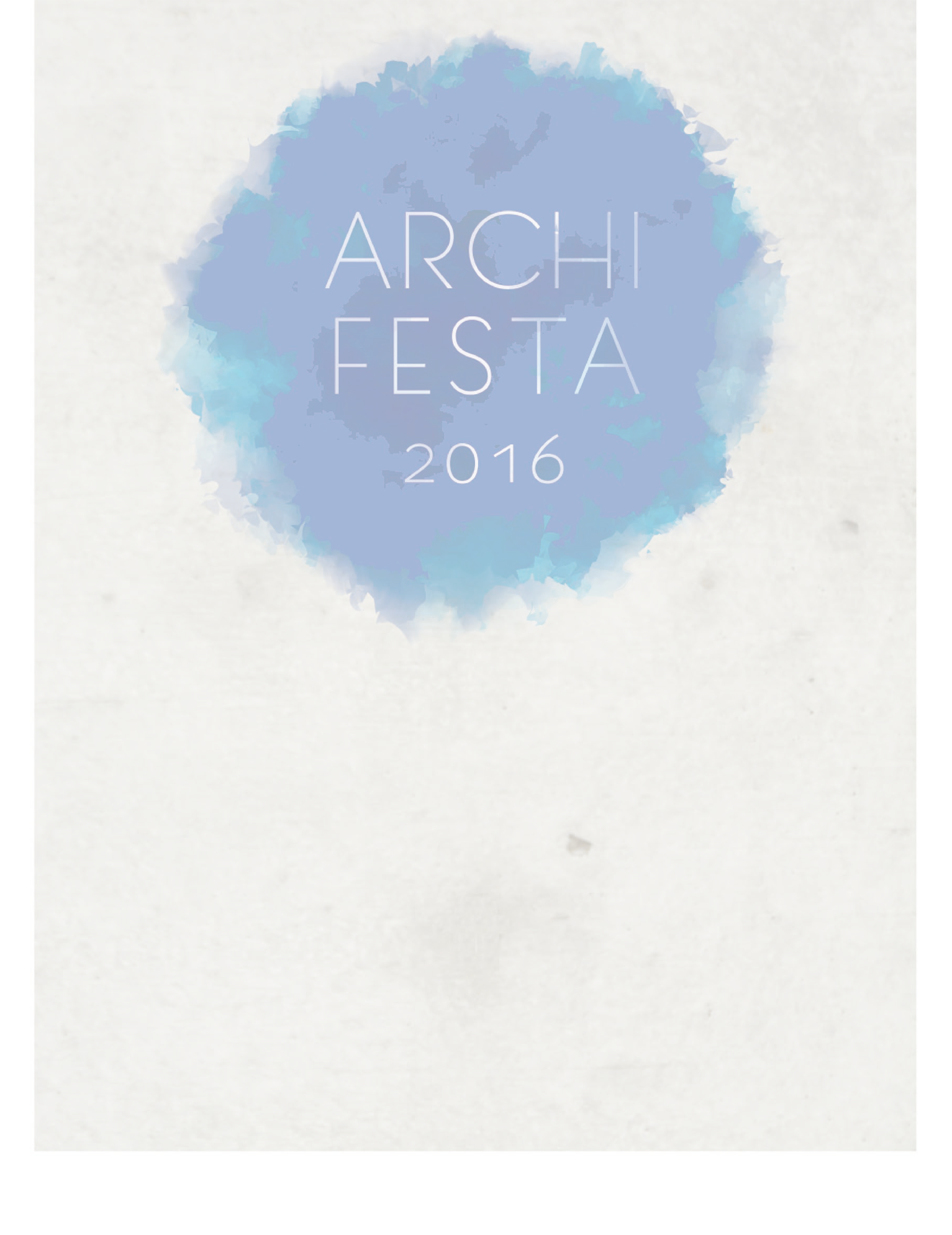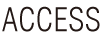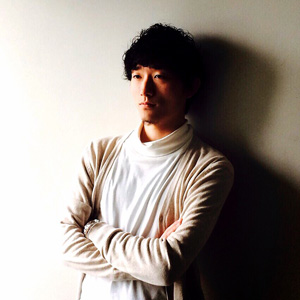 |
aj12004 |
荒木幸一郎 |
祭礼河岸ー解体される宿場町における新たなコミュニティスケールの提案ー
祭礼河岸 解体される宿場町における新たなコミュニティスケールの提案
千葉県市川市行徳。かつて宿場町として栄えた町が、人の繋がり・町の様相、共に解体されようとしている。
本計画は、解体がせまる町にFab Labを中心とした新たなコミュニティスケールを提案することで、住人自らがソフトとハード共に町の更新を行うものである。
|
 |
aj12012 |
石本遊大 |
新宿のあしもとー3つの減築手法によって生まれるまちの賑わいー
新宿三丁目のモア街と言う場所。そこは人々の居場所、さらには賑わいも失いつつある新宿において特別な場所である。モア街では人の動線が交わる、多くの世代の人が交わる、そしてまち全体の人の活動が交わる。そんなモア街に、私は3つの減築手法を用いて都市、新宿を訪れる人々の居場所となるような“新宿のあしもと”をつくり出す。 |
 |
aj12015 |
岩丸鷹也 |
死亡者0ー防火対策と住空間の豊かさの再編ー
2015年2月20日。私が住んでいた集合住宅で火災があり、多数の死亡者と重軽傷者を出した。今後、集合住宅の設計は、「防火対策」と「住空間の豊かさ」の2面性について考えられるべきであると思う。この提案は、集合住宅で火災が起きたとしても、迅速に避難ができ、死亡者が出ない「防火対策」と、「住空間の豊かさ」を併せ持つ集合住宅である。 |
 |
aj12018 |
内田有香 |
緑を溶かすー新しい駅前空間の生かし方ー
緑を溶かす~新しい、駅前空間の生かし方~生活が緑に溶け込んだ三島らしい空間が駅の周辺に広がっている。その一方、多くの人が利用する駅前にはその三島らしさが感じられない。駅前の土地の生かし方を見直し、地域の特性を設計に取り込み、地域の人そして遠くから訪れる人に愛着のもたれる豊かな空間を提案する。地域の再構築のモデルを示す。
|
 |
aj12022 |
大塚文音 |
即興劇場日本橋ー高度消費社会における消費できない空間の構築ー
ここは消費のサイクルから抜け出し、自分から湧き上がるものと対峙できる場所.劇場空間とは異なり、台本はなくみなが等しく役者であれる.様々な人々が入れ替わり立ち替わり折り重なり、自由な即興劇を繰り広げるような、様々な物語のはじまりの場所として存在できるといい. |
 |
aj12023 |
岡本隼樹 |
Hideout Sequenceー都市とゴミ処理場の接点の再編ー
都市の中には日常から切り離され、隠された風景が潜んでいる。近代以降、都市の風景は建築により分断されてきたのに対し、私は都市の風景を繋ぎ合せる建築を提案する。本計画は都市の中で隔離されたゴミ処理場を中心とする敷地に、都市のもつ多様な風景・活動を、投影・集積させ、分断された都市を再び繋ぎ合せるものである。
|
 |
aj12024 |
小川祥明 |
ポタジュが彩る都市風景ー農が隣にある都市居住の提案ー
我々が普段生活していく中で、必要な食べることを身近で感じながら生活できる、農が身近に感じられる新しい都市居住を提案することができないだろうか。すでに解体されてしまった都営宮下町アパートの跡地や当時の建物の躯体を利用し、そこに「ポタジェ」を散りばめることで、都市に新しい魅力を与える。
|
 |
aj12025 |
奥野駿 |
一寸先はヤミー吉祥寺、裏の空間更新計画ー
今日の日本では、都市の人口集中や地方の過疎化が深刻化しています。
これらの唯一の対策が田舎での人との交流にあると私は感じています。
「緑・街・人を身近に感じる事の出来る交流居住施設」を計画し、
新たなライフスタイルを提案します。
|
 |
aj12027 |
加藤賢一 |
みんなの家ー除染廃棄物を用いた町の記憶の保存ー
私の故郷、福島県楢葉町は放射能に汚染された。私たちの生活の痕跡は、除染によって放射能とともに削り取られ、黒い土嚢袋の中に閉じ込められている。町中から掻き集められた故郷の表層、それは震災前の大切な記憶であった。蓄積した故郷の記憶をいつまでも守り続けるため、みんなの記憶を用いて「みんなの家」をつくる。 |
 |
aj12038 |
小池束紗 |
千寿さがしー地域性を活かした千住地区再開発の提案ー
都心でも郊外でもないまち、千住。これまで大きな再開発が行われてこなかった新旧入り混じり様々な活動が営まれるまちであるが、
近年の大学キャンパスの新設や新路線開通などはまちに大きな変化をもたらそうとしている。予測される再開発をこのまちに寄り添ったものへと変換することでこのまちのよさを引き継いでいくための提案を行う。 |
 |
aj12041 |
小竹拓生 |
Re:Verー都市に埋もれた河川の価値の創出ー
日本の首都・東京において、都市は河川を起点に発展してきた。しかし現在、その河川は都市の裏側へ追いやられてしまった。
本計画は、これまでの都市開発の観点からは否定的に扱われ、現在では都市を分断する要素でしかない河川空間に現代の都市空間としての価値を見い出すものである。
|
 |
aj12042 |
小知和建吾 |
谷都を編むーモビリティがつなぐ人と環境ー
谷都を編む モビリティでつなぐ人と環境
まちはつながりを失いはじめている。谷戸と呼ばれる環境につくられた密集住宅地には住民たちのコミュニティスペースはなく、残された自然もまちの裏側に隠れてしまった。まちのつながりを取り戻すために、人とまちをつなぐ「コミュニティバス」と、人と人、人と自然をつなぐ「バス停」を提案する。 |
 |
aj12043 |
小林晴佳 |
堆積する都市ー縮小社会に備えた機能転換の構想ー
東京の高架道路は高度経済成長期の発展の象徴であった。しかし建設から数十年の時を経て老朽化が
表に出始めた。以来、景観の問題も重なり撤去を望む声が多く上がっている。
日本人は近い過去を軽んじる傾向にあり、このままでは文脈のない都市が出来上がっていく。そこで存在する構築物に積み重なる都市を構想する。 |
 |
aj12046 |
佐武亜美 |
WORKREARINGーワーキングマザー家族の集う住まいー
女性の社会進出が進む現代、働きながら子供を育てる母親は増えている。とはいえ都心部では、核家族であるため近くに頼れる存在がないことや、待機児童の問題も重なり、働きたい思いを実現することが難しい母親も存在する。コレクティブハウジングによって生まれる豊かな住環境と保育園の併設により、仕事と子育てを両立しやすい住宅を実現する。
|
 |
aj12047 |
佐藤翼 |
283人の地緑ー多摩NT団地における地域コミュニティの再生ー
多摩ニュータウン開発中期に建てられた集合住宅団地に対するリノベーションの提案。
近年、「ゴーストタウン」と呼ばれている多摩ニュータウン。
団地には、老朽化・高齢者にとっての住み辛さ・住民同士の交流の希薄化といった問題が見られている。
既存の耐力壁を残しつつ、非耐力壁や床を抜き減築すると共に、公共施設の増築をし、解決を図る。
|
 |
aj12049 |
澤田慧太 |
ひとづくりー高架下に集う町工場と教育ー
町工場の町として知られる東京都大田区。しかし大田区に生まれ育った私には、「町工場」という印象は全くない。住民の生活とは隔離された町工場。私の提案は中心地の人通りの多い駅前、新たに生まれた高架下というスペースに町工場と教育施設を集める。生活にものづくりが関わり身近となり創造力を育む。 |
 |
aj12052 |
柴田皓一朗 |
REFURBISHMENTー創造的修正による世田谷区庁舎の編曲ー
歴史的建築に敬意を払う態度は文化財保存という概念の中だけにあるわけではない。
クラシック音楽が時代を越えてジャズやポップスへと姿を変えたように、偉大な建築家が奏でた主旋律を残して、時代の要求に沿った編曲を行う。建築は長く生き続け、その街のアイデンティティを次世代へと受け継いでいく。
|
 |
aj12055 |
白石崚馬 |
まち・研究施設ー街が育てる町工場ー
墨田区京島の商店街に建つ町工場の研修施設。実技研修所、学科研修所があり商店街に来る人から研修している姿がみえる。また町工場の製品、研修生の作品展示室も商店街沿いに建設されている。商店街から見ることで町工場をまち全体が育む建築。
|
 |
aj12058 |
鈴木惇平 |
Slow Architectureー千葉市栄町における風俗街を段階的に再編するー
かつて商業の栄えたこのまちは風俗街へ
と姿を変え、現在は急速に衰退している。本計画はアーティストインレジデンスやSOHOなどの住戸が一体化したプログラムを段階的に作りながら人口を増加させ、栄町というまちの価値を再構築するものである。
|
 |
aj12061 |
須山隼人 |
蘇生する生業ー銚子漁港における水産業の観光化ー
産業によって栄えた日本社会。だが世間には産業の姿は閉ざされている。本計画は産業によって栄え、現在過疎化が進む銚子の水産業地域を対象とし、「観光軸線」と「拠点」の設計により水産業の観光化を提案する。そしてブラックボックスとなっている産業を可視化させ、衰退してゆく地方産業の未来へのあり方を提示することを主題とする。
|
 |
aj12063 |
平良千明 |
ウージ畑のチャンプルーーきび刈り隊から広がる交流施設の提案ー
沖縄県はチャンプルー文化である。時代的背景より東南アジアやアメリカからの影響を受け、独自の文化を築いてきた沖縄県。そんな沖縄県で、衰退しつつあるさとうきび産業を背景とし、県外からさとうきびの収穫を援農する「きび刈り隊」と市民たちの新たな「チャンプルーの場」を提案します。 |
 |
aj12072 |
田中太樹 |
劇テキ・サカ場ー北区赤羽一番街の演劇を核としたコミュニティ空間の提案ー
劇テキ・サカ場。演劇の世界を垣間見せる第三の場、酒場。そこは人間を人間たらしめる空間。猥雑で人の声が溢れ出し、皆それぞれ自分らしさを表現する。活気に満ち溢れたその空間は予期せぬ出会いを演出するかもしれない。 |
 |
aj12077 |
戴櫻 |
漂う感性ー多様性を纏うオフィス空間の提案ー
オフィス空間は作業効率を最重視し、画一的で無機質な空間になった。人間関係や働き方、 様々なものが複雑化する現代、創造性を生み出す新しい空間が求められる。再開発により大 型建築が増加する中で人々の身体性に働きかけ、意識の覚醒を促す建築空間で人と建築の 関係性を積極的なものに変えていく。 |
 |
aj12090 |
早川紘生 |
鉱都の記憶
産業革命を終え、守成の時代に入った今日、産業革命の負の遺産と呼ばれる採掘跡は立ち入りが禁止されるなど、人の目から隠されてきている。しかし採掘跡をただ隠してしまうことは正しいのだろうか。植林により採掘跡が隠されつつある埼玉県秩父地域の武甲山を敷地とし、鉱山都市の記憶を採掘跡が隠される未来に伝える場所の提案である。
|
 |
aj12096 |
深山亜耶 |
大地の潤いーグリット都市札幌におけるヒトのためのケモノミチー
暮らした街なのに答えられない。特徴が無く思えるのはグリッドという強烈な特徴に支配されているからではないか。札幌にはかつて川が流れており街の発展と深く関係していた。川跡をヒトが歩くケモノミチとして甦らせ川の有機的形態から生まれる場所に建築を提案する。人の為にできたケモノミチが街に潤いをもたらす。 |
 |
aj12097 |
福山ふみの |
優しい終い方ー過疎地域における集落消滅までのデザイン設計ー
少子高齢化が進行する社会を背景に消滅可能性地域の拡大が問題視されています。地域活性化は全ての過疎地域にとって有効な手段とは言えないでしょう。私は、1つの選択肢として町の終わらせ方 −−−「 終い方 」を提案します。終わりに抗うのではなく、終わりを受け止めた建築設計をすることで見いだせる豊かさがあるのではないでしょうか。 |
 |
aj12099 |
古田咲貴 |
織りなす軌跡ー都市更新にともなう駅前複合施設の計画ー
近年、都市機能の更新を図る目的で「再開発」が行われている。本計画では、草加市に建つ松原団地の再開発に伴った駅前複合施設の在り方を考えていく。その地域が培ってきた生活や文化の価値を継承したまちづくりの一環として、その地域を利用する人の動きに着目し、新たに生まれ変わるまちに寄り添った機能をもつ施設となるよう計画していく。 |
 |
aj12102 |
松井佳子 |
緑繋ぎのまちー孤独死を予防する単身者の住まいー
「孤独死」ここ数年よく聞くようになった社会問題だ。これは様々な問題が複合的に影響した結果起こっているとても悲しい現象だが、私は本来安らぎを与える場所であるはずの住居がそのような問題の現場になっていることに最も悔しさを覚える。この現状を、住環境に何か操作をすることで少しでも改善出来ないかモデルケースを考えてみた。
|
 |
aj12109 |
宮澤伸行 |
纏うまち
まちが細分化され、住宅が囲障を必要としなくなり、囲障がはがされていく。その剥がされた囲障を空間化し、住宅と組み合わせることにより住人の生活に絡ませていく。この建築らによって共有空間と専有空間を明確に仕分け、豊かで快適な共同生活・住環境を目指す。
本計画ではこれからに向けた新しい囲障の姿・役割を提案したい。 |
 |
aj12111 |
森遊耶 |
薄都濃村ー道の駅の転換による地方再生ー
21世紀の今、「農村部」の過疎化が著しい。
地方再生のために政府は道の駅を増やし続けているが、活性化に繋がっておらず、地方自治体の負の遺産にさえなっている。
全国に点在する道の駅を解体し別の質に転換させることで、都市部と農村部の関係に変化をもたらし、地方再生もとい、色濃い地方未来を描く。
本提案は都市と農村の狭間の建築である。 |
 |
aj12112 |
森野航平 |
都市の潮汐
「流速」という視座からの建築の模索。
経済合理主義の定めなのか、容積が目いっぱい満たされた建築によって神田美土代町は大変息苦しい都市空間となってしまっている。人の溜まる場所もないため、道ゆく人の足は早い。本計画は、人の流れ、とりわけその速さに焦点を当てた計画である。建築が速さに介入することで、質の高い都市空間を創出する。
|
 |
aj12113 |
森本友理 |
おわり。はじまり、ー小学校跡地を舞台とした公共施設の複合化の提案ー
老朽化する公共施設を多く抱え、更新法に悩む杉並区への提案。廃校となった小学校の跡地に「幼児・高齢者地域の女性」のための3つのプログラムを集約。小学校のRCの躯体を減築しながら、木造で空間を補修する事で、外部と内部を刺激するような建築を設計する。 |
 |
aj12117 |
山田香澄 |
終わりへ向かう始まりの街ー元気高齢者が活きる未来ー
技術は進歩した。巡る交通手段、連なる高層建築。けれど暮らしは豊かになったのだろうか?医療技術の発展んで伸びた元気寿命。開発の波に飲まれようとしている街から始まる元気高齢者が生きがいを見つけて活きる、学校の提案。 |
 |
aj12124 |
吉成祐貴 |
Agri-urban-cultureー都市農業拠点の再編ー
この提案では、都市の人たちに農業を知ってもらうきっかけの場を生み出すことを目的とする。都市での農業は多面的な機能を有することから重要とされるが、現状では失われつつある。農業試験場とその周辺を一体的に再編することで、都市における新たな農業のカタチを創出する。 |
 |
aj11061 |
須永杏 |
AEONIC COMMONー地方型大規模商業空間をもとに公共空間へ変容する実験建築ー私の街には大きなAEONがある。余暇を楽しめる場所が限りなく少ない地方都市では、AEONは人々の多彩な公共性のある活動を生む。しかし、AEONは利益が下がり出すとその街から撤退してしまう。AEONを商業施設から公共施設へ転換し、AEONに公共性の継続の道筋を示す。そして、AEONを街に還元する。 |