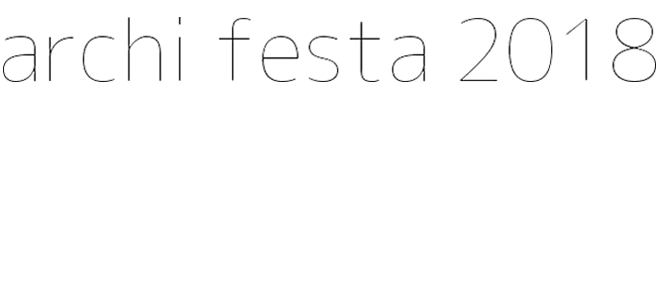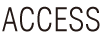建築学科/ 建築工学科/ 環境システム学科/ デザイン工学科/
■建築学科
| image | overview | ||
|---|---|---|---|
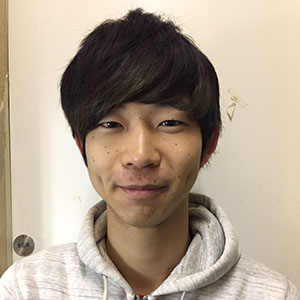 |
aj14006 安藤裕次郎近年の消費をベースにした都市開発により密度を重視した高層マンション、オフィスビルのような場所性を問わない建築物が蔓延している。 敷地は新宿区四谷荒木町の四方が丘に囲まれたスリバチ状の窪地である。しかし、再開発によって周囲に高層マンションが建設され場所の個性が失われようとしている。荒木町の文化、特異地形を綿密に調査し、この場所でしか成立しない建築を提案する。 |
||
 |
aj14007 池田健吾
穢れの空間は社会的に排除される。共同体の薄れにより増え続ける「孤独者」。社会現象の一つとして成り立ってしまっている無縁の死の拡大。つながりを失ってしまった人の居場所は生前も死後も存在しないのだろうか。無味乾燥とした歴史の無い土地、辰巳一丁目団地。ここで孤独者の生きていた記憶を蔵書として地域に継承していく。偶然生まれる故人との対話が、人々に「継承者」という役割を与え地域をつむんでいく。 |
||
 |
aj14008 石川達也保育園で過ごす0〜6歳は人格形成期と言われ、その時期に多様な人、ものに出会うことがこどもにとって重要だと考えられている。しかし、現代の保育施設はこどもの安全を重視するため柵で囲まれていたり、ビルの1室に多く存在し閉鎖的になっている。設計では、こどもと大人が交流するきっかけの場、機能を設けることによって保育園が地域に開かれたものとなる。人生の始まりの6年間を様々な出会いがあり、経験を積んでいく。 |
||
 |
aj14011 石上篤樹東日本大震災以降、福島県郡山市は単身世帯が増加している。「福島県は汚い」という風評によって子を持つ世代の転勤族が郡山赴任の際単身赴任という選択肢を選ぶようになったためである。彼らのための集合住宅と商業の複合建築を提案する。ネガティブな事故から生まれた要素を逆転し用いることで衰退している市街地に新しい暮らし方を提案することで郡山市市街地活性化の起爆剤となる。風評被害に負けない都市をつくり出す。 |
||
 |
aj14022 岡本結里子「触る」を意識することは周囲の世界をもっと知ることだけでなく、自身の体や、その物事を捉えるやり方について新たな発見をもたらすとされている。一方福祉の世界ではフラットであることは清潔さを維持しやすい事から肌理は排除されてきた。現在超高齢化を目の前とした日本では多くの老人が福祉施設へ入居している。建築的肌理の採取により終の棲家として過ごす場所に肌理を挿入し触れることで、より豊かに人生を謳歌することを目指す。 |
||
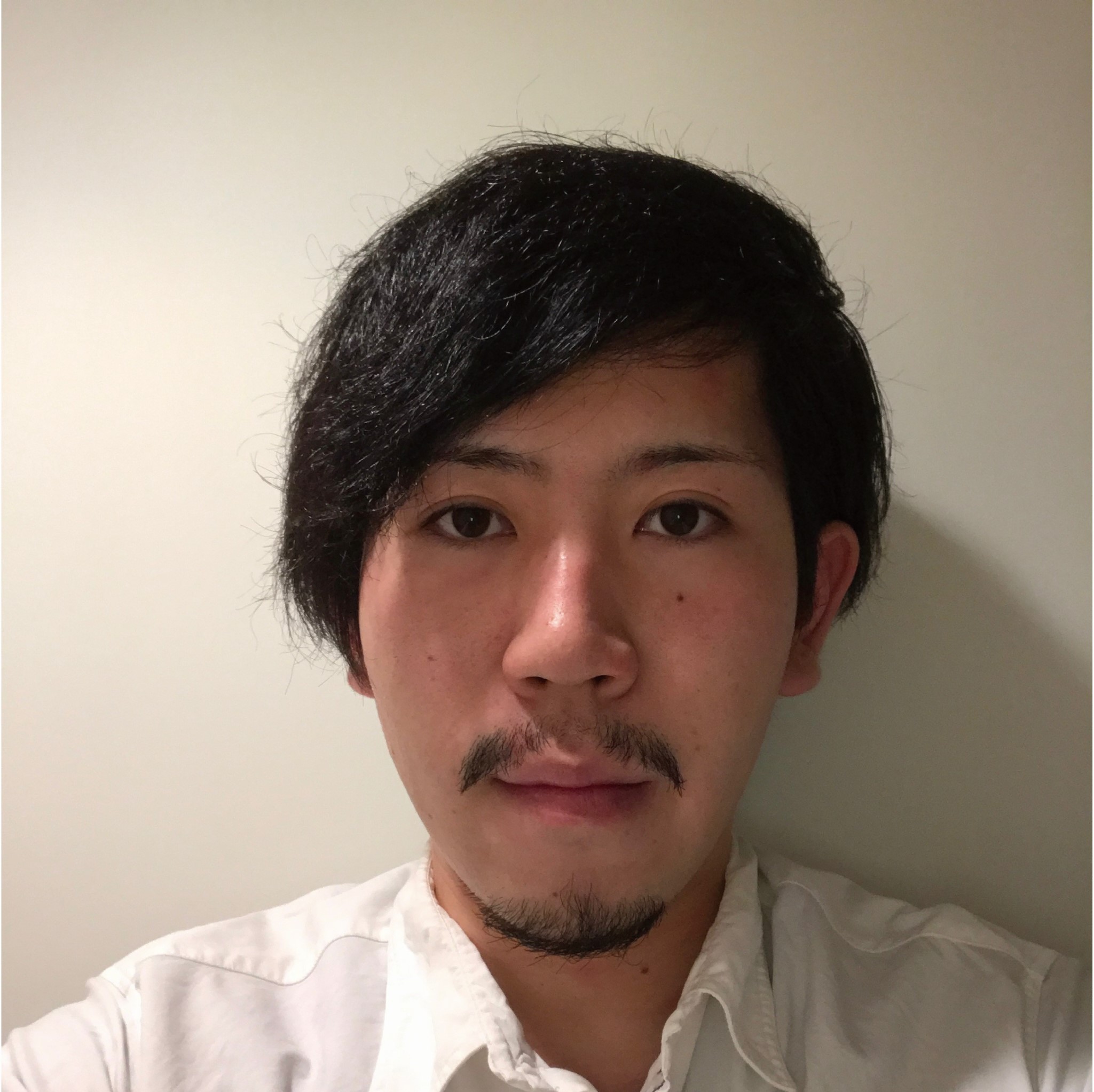 |
aj14034 工藤滉大私の生まれた青森県弘前市にも盲目に発展し続ける現代社会の荒波は押し寄せる。場所も他者も必要のない、自分の欲望をただ叶え続けてくれる社会は本当に豊かな社会であると言えるのだろうか。利便性を追い求めたこの地には孤独を覚える市民が増えていた。この地に自然と人々の対話が起きる場所を提案したい。豪雪地帯である弘前の人々には雪かきなどの不便を日常に包容する習慣があった。これが本設計の始まりである。 |
||
 |
aj14036 久保田柚子群馬県伊勢崎市境地区。私の地元であるこのまちには高校がない。ほとんどの人がまちの外の高校へ行き、その先は地元を離れる。そんなまちの記憶は、まちで過ごす時間の多い小学校の時のものばかり。そんな小学生が毎日歩いて登校をする通学路に視点を当て、それをもっと充実したものにすることで、まちの思い出も増やしていく。みちが記憶を作る。小学生が気軽に寄り道できる場をまちに点在させ、まちの様々なみちを練り歩く提案。 |
||
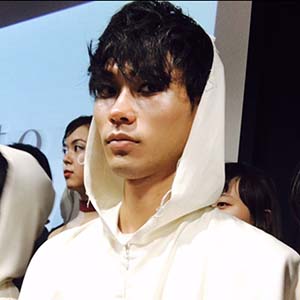 |
aj14038 小池正夫人それぞれお金の価値は異なるにも関わらず、家賃システムしかない社会では多くの可能性が消えている。家賃システムの他にも、空間を手にする方法があるべきである。スクワッティング運動を基に、お金の代わりに地域に賑わいを与えることで住居を手に入れる方法を提案する。寂れた街の空き商店を学生が次々とスクワットし市民が利用できる大学施設にする。小さい操作で街を変えることができるDIYのモデルケースを設計した。 |
||
 |
aj14039 小泉菜摘日本は深刻な血液不足を迎えており、2027年には血液需要がピークを迎え医療崩壊を招くと言われている。一方、社会を流通する献血血液量は、見方を変えると誰かの命を思った心の量そのものであり、血液を集め社会へ供給する献血施設は「社会の心ぞう」と捉えられる。歴史が浅く、土地性や人の関係性の薄い豊洲に食の概念を加えた献血施設を設計することで、血がめぐり地に根付く新しい縁の社会を構築する 。 |
||
 |
aj14040 河野祐揮名前を連呼する街宣車に、単純明快なキャッチフレーズで政策を打ち出す候補者。選挙の度に展開される政治言語ゲームに日本の有権者は翻弄される。経済的にも成熟した日本は社会に対する不満も少なくなりメディアが伝えるのは政治ゴシップネタばかり。日本全体が政治そのものに無関心になってしまった。政治というものをもっと身近なものにするために政治をリアルタイムに可視化した建築と政治に対して主体性を喚起する舞台を作る。 |
||
 |
aj14042 児玉美友紀物理的に存在する現実の世界と私たちの頭の中にある仮想の世界、その境界線がテクノロジーの発達によって急速に曖昧になり、個々人の間でのずれが生じ始めている。区役所という、社会のシステムを取り扱う施設の設計を通して「私たちはそもそも仮想の中で生きているのではなかったか」を問う。仮想空間によって建築が解放され、人々が集い、共に過ごし、語り合うアゴラとしての本質を取り戻す。 |
||
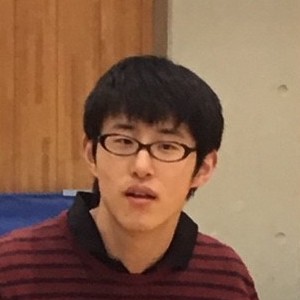 |
aj14054 澤智己 今、郊外では発展に陰りが見られ始めている。活力を失う農業、高齢化が進む団地、関心の向けられない保育の場。東京都心のベットタウンである東京都東久留米市において発展と共に多層化した市民はそれぞれ問題を抱えている。今必要とされているのは開発により外から人を呼び込むことではなく、その場所における魅力を共有し、市内での居住者の循環を促す内側からの活性化である。郊外住民をつなぐ新たな拠点の提案。 |
||
 |
aj14056 荘司知宏1925年に開港した日の出埠頭は、東京港で最初に開港した埠頭として貨物線、船舶ともに物流の拠点を担ってきた。しかし現在、物流機能は他港へ推移し、人の姿は減り、また海が近いことも活かされてない風景が続いている。周辺の再開発も加速する中で、孤立したこの地に、空洞化した倉庫群を活用し、新たな埠頭空間を提案する。 |
 |
aj14061 嶋田康志現在、情報化が進み、関係の希薄化が進んでいる。そんな今だからこそ、人や物との出会いによって生まれる経験が重要である。人と人をつなげる、新しい出会いを生む建築を考える。私が生まれた育った町福岡には、移動式屋台がある。屋台は、夜になると現れ、朝になると消える。そんな屋台が生む偶発的な出会いに惹かれ設計を始めた。屋台の偶発的出会いの要素を用いて、かつて出会いの場出会った中洲を再編する。 |
 |
aj14064 杉沢優太京成立石駅周辺は再開発によってそのまち並みは大きく壊されようとしている。その背景には、建築の老朽化、経済的な理由がある。だが、利用者の視点からすると、建築は地域への愛着などを拠り所とする人々の記憶の器であり、アイデンティティの一部を形成しているものである。再開発が進む今、一度取り壊したら取り返しのつかないものもある。本提案により再開発ではない過去と現在をつなぐまち並みの更新を提案する。 |
||
 |
aj14067 関紗綾香長野県稲荷山地区。重要伝統的建造物群保存地区に指定され、このまちは変わり始めた。オモテだけが均一に整えられた街並みがこのまちの目指すべき姿なのだろうか。集う図書館、活動するアリーナ、まちを見渡す展望塔。まちのオクに生まれるこの建築に、すきまから人々が入り込み、すきまからまちへと活気があふれ出す。それがやがてまち全体へと広まり、私の知らないオクの世界がつくられていくことを期待し、私の創案を提示する。 |
||
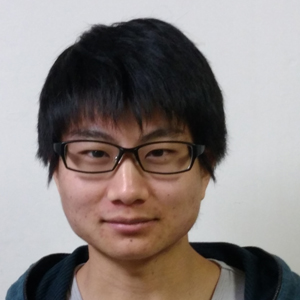 |
aj14073 高田瑞貴宇都宮市は地方都市構造の変化に対応するべく交通ネットワークの再編を計画している。その再編に伴い、多種の交通の結節点−トランジットセンターが生じる。その点は交通のみではなく、人々の結節点となる可能性を含んでいる。人間の多様な活動にも焦点を当てトランジットセンターを設計することで、日常の移動の中に、人生に彩りを与える生活地を生じさせる。 |
||
 |
aj14076 高橋一成東京都台東区 山谷地区。かつて日雇い労働者が生活し活気に満ちていたドヤ街は、労働市場の縮小と高齢化により、生活保護受給者などの貧困の街へと変わっていった。そこでドヤという三畳一間、風呂・トイレなしの空間で暮らし、あらゆるものを持たざる彼らの生活を補完していく生活拠点を提案する。空き地や空室に挿入されていく仮設建築は、生活機能のネットワークや情報、知識の共有など街の隙間に新たな日常を生み出す。 |
||
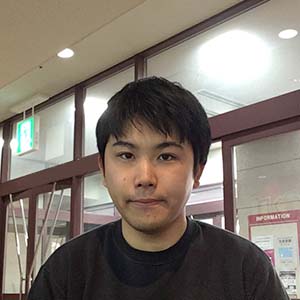 |
aj14084 中嶌健人清掃工場は巨大密閉型施設という特徴を持つことから、地域から嫌煙される存在(NIMBY施設)となっている。このように嫌煙される存在を、いかに地域(マチ)と調停するか考えることを本計画の目的とする。対象として江戸川清掃工場を選んだ。提案は、嫌悪施設を地域と調停すると共に、郊外としてファストフードのように消費されている敷地の問題とも向き合っていく。 |
||
 |
aj1408 中曽根紫帆サブカルの聖地、下北沢。個性の塊のようなまちで今、2つの再開発が行われている。この再開発では主に、線路の地下化と都市開発道路の建設が行われる予定だか、これによる大規模な市街地の破壊と都市化を問題視する声も上がっている。地域のアイデンティティを守りつつ、活気のあるまちであり続けるための再開発に、一つの未来像を私は提案する。 |
||
 |
aj14088 中原惇之介多様な場面でリスク排除が求められている世の中、子供達にも影響が出ている。多くの公園ではボール遊びが規制されていたり、色々な事が規制されている。このままでは、子供の遊ぶ場所はどうなってしまうのでしょう。遊びという必要なリスクから遠ざけられ安全に育てられた子供達は、体力の低下とともに、引きこもりや、自殺、生活習慣の乱れなど、様々な問題の真ん中にいる |
||
 |
aj14090 中村靖怡災害が起きた場合、最も懸念されるのは水の確保である。震災時に給水管が破損すると、水を得る手段が途切れてしまう。見えない巨大設備に依存するのではなく、身近に小さな見える設備との併用をすべきである。木造密集地域である東京都墨田区において、小さな防災拠点を提案する。雨水を構造体に貯蓄し、構造と設備が一体化したシステムを作り出す。町—建築—インテリア—プロダクト、様々なスケールで雨水が生かされてゆく。 |
||
 |
aj14096 野上伊織人・都市・水辺の関係を考える。都心と地方の中間に位置する衛星都市、いわゆるベッドタウンでは、都心と同じく人と都市の関係が強い。千葉県柏市にある「手賀沼」。かつてはウナギの住処になるほど綺麗だった沼の水も、今では汚濁度ワースト3位にまで水質が悪化している。そこで市民が「水辺に集い、水辺を追憶し、水辺で再発見する場」を、手賀沼浄化の過程を通して経験させる。 |
||
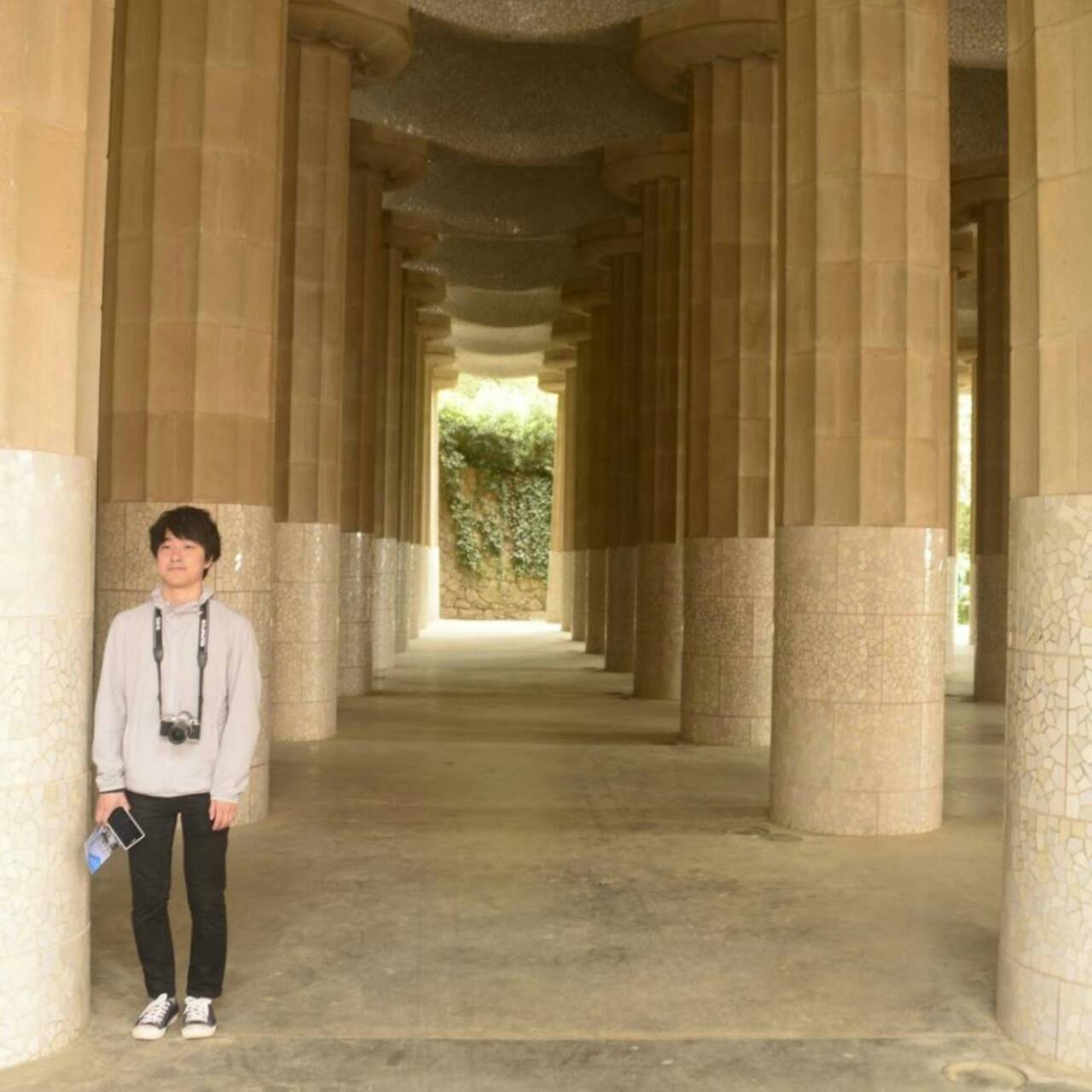 |
aj14099 ICTの普及や価値観の多様化を背景に様々な暮らしが見られるようになった。そこに時間、場所、組織に縛られることなく働くノマドワーカーと呼ばれる人たちがいる。しかし社会的な評価が低く、収入の不安定な彼らを受け入れる住宅はあまり整備されてないのが現状だ。そこでノマドワーカーの働く環境が整備されている渋谷を敷地とし、ここに流動的に働く彼ら一時停止の場としての住宅を提案する。 |
||
 |
aj1411 堀場陸社会は逃げ場を欲している。我々は何かに迫られ、追い詰められたとき、それから逃げようとする。しかし、そこに逃げ場がなければ、逃げることができない。建築というものは、人間を閉じ込める箱であり、空間には逃げ場がない。現状の空間を階層的で一方通行な「ツリー形式」と定義し、その形式が顕著で逃げ場のない中学校において、新たに複層的で選択可能な「セミラティス空間」を提案することで、逃げられる空間を実現する。 |
||
 |
aj14111 真角恭平近年、再開発によって都市に元々あった居場所が失われているのではないだろうか。 東京都大田区蒲田では駅を中心に再開発が盛んに行われている。しかし、その一方で多くのホームレスの人々が生活している空間や昔ながらの飲み屋街などが失われ、かつて蒲田にあった人々の居場所が少なくなってしまっている。変化を続ける街の中で、多様な人々が豊かな生活を行うことを可能とする都市の居場所を提案する。 |
||
 |
aj14112 増村朗人合理的な目的達成を是とした近代化で失われた『想定外の〈出来事〉との遭遇』を追求した。人口流出・高齢化・モータリゼーションの進む豪雪地帯の長岡で、協働を伴い積雪時の歩行者空間を育むふるまいを内包した建築群を提案する。市街を流れる信濃川水系の河川まわりから始まり、建築は敷地を超え連鎖し長岡の日常を彩ってゆく。 |
||
 |
aj14116 三浦桃子ダンスとは身体行為共有によって、感情を共有できるノンバーバルコミュニケーションである。国という壁を越えて、距離を縮め、互いのより深い理解を促してくれる。ダンス的コミュニケーションにおける重要な要素である”行為共有”を建築の操作で誘発させることで、人々は身体コミュニケーションを取ることになる。そのような”踊的空間”を、多人種であるが小交流な都市「浜松町」にできる産業貿易センターに”挿入する。 |
||
 |
aj14121 毛利慶都市生活においてもっと身体的にも精神的にも豊かになるような活動とはどんなものだろうか。商業地域、官庁街、住宅街が入り混じる本千葉駅周辺地域において『銭湯』を核とした様々な人々が集まるスポーツ施設を考える。この地域に住んでいる人、この地域で働く人、この地域にくる人がスポーツを通して汗を流し、最後に銭湯で混じり合うことで都市における生活が豊かになるような新たな縁の創出の場を提案する。 |
||
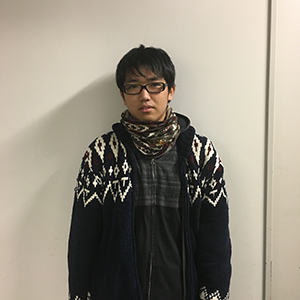 |
aj14128 吉田圭吾東京都墨田区京島。この地区は、東京の下町が焼け野原になった東京大空襲を奇跡的に免れた地区である。なので、戦前の古い木造住宅が現存しているが、それはすなわち、老朽化した建物が存在していることと同義であり、現在、再開発が進められている。しかし、その再開発により、古い下町の街並みが破壊されてしまっている。そこで、京島の良さを取り入れつつ、防災も加味した建築物を提案し、この再開発に歯止めをかけていきたい。 |
■建築工学科
| image | overview | ||
|---|---|---|---|
 |
ak14001 赤司康太伊豆半島に位置する熱川は、経済成長によって盛衰のあった温泉街である。成長と共に高層の宿泊施設が立ち並び、かつての湯治場としての温泉の役割は変わってしまった。かつて温泉地には日常の束縛や規制に溢れた都市から離れ、異郷の人やそこでの付き合いを楽しむような湯治空間があった。観光経済の潮流の中での、新たな湯治場として熱川の再編をする。 |
||
 |
ak14006 有村滉貴私の祖父は鹿児島県知覧町に住んでいる。物心つかない頃から遊びに行き、現在も訪れる小さな田舎町だ。今でこそ平和でのんびりした時間が流れているが、ここにはかつて大日本帝国陸軍知覧飛行場が存在し多くの若者が家族のため、特攻隊として飛び立っていった歴史がある。飛行場跡地は現在畑や住宅地が広がっており、面影は消えかかっている。忘れてはいけない戦争の悲惨さを、建築を通し、後世へと語り継ぐ。 |
||
 |
ak14014 井上航太かつての日本には入会権などの伝統的な地域制度が存在し、山林や河川などの自然資源の共同管理を行ってきた。しかし市場経済の侵入により制度が徐々に崩壊し、自然資源との関係性も希薄になっていった。地方都市の衰退が進む中、余暇活動を行う人々に可能性を見出し、かつての木材輸送の経路であった埼玉県飯能市の入間川の河川沿いに地域産業であった林業の複合施設を展開し、自然資源との関係を取り戻していく計画。 |
||
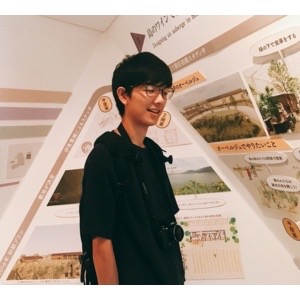 |
ak14028 川邉幹寺院は古くは子どもたちにとって重要な空間であった。江戸時代に遡れば、寺子屋として農民などの身分の低い子どものための教育空間として機能していた。寺院自体は現代にもその姿を残しているが、寺子屋はやがて小学校という建築形式に移り変わった。現代における子どもたちは情報機器などの発達により外遊びをする機会が減ったりするなど好ましくない状況を抱えている。いま、寺院から子どもの居場所を再考する。 |
||
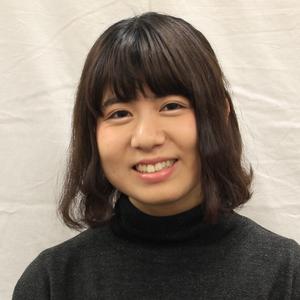 |
ak14032 岸晴香友人の一回忌にて訪れた地方の墓地で、区画ごと荒れ果てたお墓が私の目に留まった。近年、故人や人の死に対する価値観が薄れ、先祖崇拝が途切れようとしている。そこで、非日常(墓地空間)と日常(人の生)の距離を縮めるべく、故人の永続を可能とする新たなシステムからなる墓地公園の提案を行うことで、今後より一層の深刻化が確実となっている墓地問題に改善を促す一手を打つ。 |
||
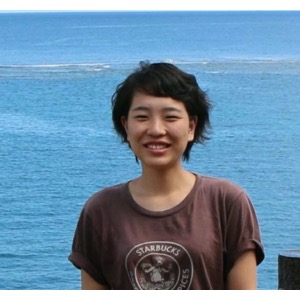 |
ak14033 北浦由樹社会の変化に伴い、子どもたちのあそびは変化してきた。そのあそびを捉えなおし、子どもたちにとって最良なあそび・まなび空間を創造していく。生育環境が十分でない子どもとその親が、ひとり暮らしまたは夫婦だけで暮らす来間島の高齢者と一緒に暮らし、島に伝わる伝統的な農業を担っていくことのできる空間を提案する。これにより、親子は理想的な生育環境を、高齢者は共に住む人を得ることができる。 |
||
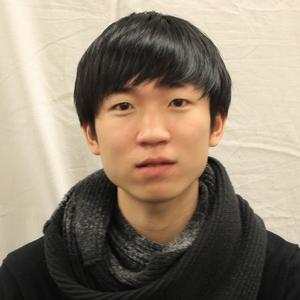 |
ak14038 小泉亮輔僕が生まれ育った故郷、千葉県野田市。醤油醸造と農業の町。美しく混沌とした醤油工場群に囲まれた野田市駅に畑を複合させアグリステーションを提案する。アグリステーションはコミュニティと風景を生み出す都市装置となり、確かな個性と共に次なる野田市の未来を描く。 | ||
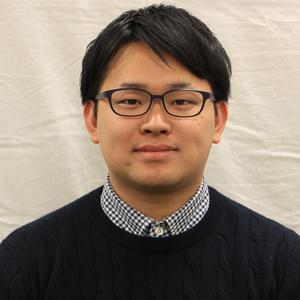 |
ak14049 坂本健悟こどもは冀望(きぼう)だ。しかし、冀望たちは絶望として地域から拒まれる。無理やり作られる居場所は壁に囲われるか、ビルの中へ。こどもの居場所をこのままにしてはいけない。ただ働きたい親が預けるための施設はこどもの居場所とはいえない。こどものための施設を作らなくてはならない。そこにちょっと工夫を加えれば、きっと地域の冀望にもなれるはずだ。冀望が通う、そんな居場所を提案する。 |
||
 |
ak14050 佐久間隆広地元の駅を降りるとすぐに石垣で周りをぐるりと囲まれた児童養護施設のエ リザベス・サンダース・ホームがある。「人生は自分の手で、どんな色にも塗 り替えられる。」施設の創設者である澤田美喜さんの言葉である。施設を地域 に開き児童の存在を認知してもらうことによって施設で育つ多くの児童が里親 の子供として暮らせるように、そしてここで暮らす児童が多様な人々との交流 の中で自分の色を見つけられるような場所を提案する。 | ||
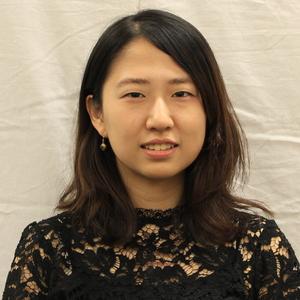 |
ak14060 島田真希バスを降りる。突如3つの塔が顔を出した。旧横浜競馬場一等馬見所。中に入ればそこは別世界。廃墟として止まっていた時間が動き出したみたい。外に出たら公園だけど、今日はチケットを買ってギャラリーに行こう。階段をぐるぐる登る。最後の扉を開けると横浜を一望できる景色。順路をたどって下に降りる。トップライトが回廊を照らす。公園に走っていく子供達のあとを追って外に出た。振り向くと過去と現在が重なり合っていた。 |
||
 |
ak14063 杉浦豪
皆さんは天然物と養殖物が同じ場所に売られていたら、どちらを買うでしょうか?ほとんどの方が天然物を好むでしょう。現在、養殖物の方が天然物より優れた品質である商品が技術向上により市場に出回り始めた。しかし、生産者の取り組みが情報時代にも関わらず、理解されてない現状は、生産者と消費者が密接に関係していないことに問題があるのではないか。「商品品質」を双方が協同で向上させ、理解し合う場を提案する。 |
||
 |
ak14067 銭元由哉
愛着のある場の消滅。心の拠り所である遊園地、としまえんが防災公園へと変わる。従来の大空地を有する防災公園は、日常時に地域住民に使われることは少なく、単なる空地となってしまう事が人と場との縁を切ってきた。それは被災時における安心感、その後の生活に悪影響を与えるのではないだろうか。遊園地跡地を被災時に対応できる防災公園としての機能を備えつつ、地域コミュニティと場の縁を結ぶ空間として再構成する。 |
||
 |
ak14070 高橋唯
都市に大きく穴が空いたかのようにある米軍所沢通信基地は、都市において閉じた空間である。人の姿はほとんどなく、閑散とした景色が広がっている。かつて日本初の飛行場として開設されたこの敷地に、飛行場としての歴史と通信基地としての歴史を未来に伝えると同時に、自らが住んでいるベッドタウンの将来を住民自らが議論する場を提供することで、跡地が住民の考えや学びを活かして形成されていくことを目指す。 |
||
 |
ak14078 外山諒介
現代では利便性の向上、情報化社会の進展、労働形態の変化により生活習慣病やうつ病が増加し、最悪死に至る可能性がある。これは運動不足が1つの要因である事が医学的に証明されている。特に災害危険地域で生活する人々は自身の力で避難するために日々運動するべきである。江東区の砂町地区は木造密集市街地と海抜0m地帯である。年々人々の防災意識が気薄化しているため、私は防災意識を養いつつ運動できる避難場所を計画する。 |
||
 |
ak14079 鳥越貴良
新宿駅。7路線8駅が集結し、世界一の乗降客数を誇る。オフィス・ホテル街、歓楽街、日本最大の一大商業地に囲まれ、数百万人が蠢く。広範囲に張り巡らされた地下網、駅に寄生する商業施設が街の発展とともにツギハギに形成され、街の結節点となるべき新宿駅は迷宮と化した。そこに北口を新設する。新たな口の存在は新宿駅に新たな人の流れを生み出す。人の流れが変わり、街が変わる。 |
||
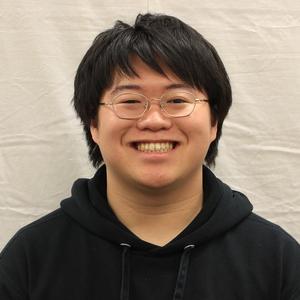 |
ak14087 西丸健
|
||
 |
ak14092 早坂美祐
高校二年の頃、仲の良い友達は私に言った。「自分、性同一性障害なんだ」。主にLGBTと言われる彼らは、差別されることも少なくない。自分を偽れ。気づかれるぞ。怖い。私は本当の自分を教えてくれた友達に感謝している。彼らが自分らしく生きれる社会になって欲しい。LGBT配慮が進んでいる渋谷で、そのきっかけとなる交流施設を提案する。 |
||
 |
ak14094 樋口雅樹
かつて水辺は人々の生活のすぐそばにあった。しかし、時が経つにつれて、私たちの生活を守るために堤防が建ち、水辺との距離は遠ざかっていった。堤防はその高さゆえ街を閉鎖的にしてしまう原因となっていた。人々が水辺を身近に感じ、街は開けていくべきであると考える。今まで「行くことのできない・行ってはいけない」と感じさせていた場所に人々が「行こう・行ってもいいんだ」と思える『きっかけの建築』を提案する。 |
||
 |
ak14106 松坂隆
豪雪都市において冬の降雪は都市を美しく彩る一方で、郊外への除雪という避けられない試練を私達に課す。年間積雪量6mの豪雪地域に190万人が暮らす、世界的にも類を見ない大都市、札幌。都心に降り積もる雪を高密度化する建築へと集積、複合することにより都市と自然の圧倒的なスケールの中で、雪と人がユキ交う、ここにしかない、新たな雪国の都市像を描く。 |
||
 |
ak14107 眞鍋啓
私の故郷、横須賀。この街には敗戦によって持ち込まれた米軍基地が存在する。基地はゲイテッドシティとなり、日本と隔絶した。日本人は自国の土地であった場所への入場を制限され、米国人はゲート内が唯一の居場所となった。協力関係にあるはずの2国は並存してはいても共存しているとは言いがたい。国と国を分かつ境界線上に互いの居場所を創出することで、真の日米関係を築く。 |
||
 |
ak14078 外山諒介
現代の日本は世界的にみて、人々が孤立している。人は一人だけで居続けることで、自分 の存在意義を消失させてしまう危険がある。しかし、同時に職場や学校という義務でいかなければならない場では、人々の関わりには問題が起きている。様々な一人が集まる池袋を対象敷地にとり、各々が個人としていられることが当たり前になれる公共空間を提案する。 |
||
 |
ak14112 横山朋美
時代の変遷とともに農業用水路、排水路と様々な姿に変化し、現在環境用水路として街中に存在する日野用水路。しかし日野用水路は急速な宅地開発により消滅の危機に瀕している。日野用水路網を3種の水質の異なる生活用水路へと浄化し、浄化されていく水路を辿った先で出会う |
■環境システム学科
| image | overview | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
br14015 石塚慈生2020年に東京オリンピックが開催される。しかし臨海副都心のその後のビジョンは不透明なままである。敷地は臨海副都心青海地区。東京五輪後のビジョンが最も不透明である 方、大型客船が停泊する新ふ頭が計画されており多くの外国人観光客が訪れることが予 される場所である。この計画を利用し、東京五輪以降の青海地区のビジョンを示す建築 創造する。 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
br14016 石橋忠司築地場外市場を対象に、小売店の働く環境を再編集する。築地市場の周辺に約400店舗が群をなす場外市場では、昔ながらの小売店が減少し、かつてあった仲間同士の繋がりや食に関する職人の技が失われつつある。そこで、場外市場で働く人々だけでなく、そこにやってくる人々との間にも繋がりを生み出し、築地ブランドを継承・発信する新たな商い空間を提案する。 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
br14023 梅田歩昂情報化社会において私達の身体行為は予定調和な傾向を強め、コンテンツ享受の多くは情報空間に集約された。そして、都市動線は日々発達し、目的地間を迅速に結び、それらの傾向を助長する。大田区蒲田もその例外ではない。蒲田駅と京急蒲田駅との800mの距離 を地下で結ぶ新線計画が進行している。地下に計画される新線の地下環境を地上の空間へと波及させ、来たる蒲田に新たな形で身体行為を還元する建築を生む。 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
br14025 大井彩有里錦糸町を舞台に、全ての人が境界なく生活できる新たなエスニック・タウンを提案する。まち同士があらゆる交通でつながることで都市の可能性が広がる現代。そのシステムをまちに落とし込み、都市空間構築の陰で分断した地域同士の道を地下でつなぐ。多様な地上の要素が集結した地下空間ではまちを一望できる。その空間はまちづかいの変化を誘発し、人々の生活の可能性を広げる。 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
br14059 篠田航介東京の合理的な都市計画によって生み出された大量のオフィスは、地域とのつながりが希薄な現状である。私はその過程で都市の裏側になった川を東京の資源として捉え、地域の拠点にする。従来のオフィスとは異なるシステムを用いた働く場を提案することで、人々の行動が新しい行動を誘発し、地域の多様な要素をつなげる川の新しいあり方。 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
br14060 白石カヤこれまでの「既に起こったことに対して応急措置を施す=feedback」技術だけでは将来の災害に対応できない。そこで、ハード的・ソフト的に未来を予測し芸術的側面を持つ建築デザインが災害工事の未来を担う。それは地域の風土を育むような、理性的で強靭なものである。非常時に人の身体を守り常時は地域の拠点となる、宿泊機能を持つ公共空間の提案。 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
br14074 外山健汰
地域固有の資源を認識し、それらと親しむことで、その地域のシビックプライドは醸成される。そこには風土や文化を体験する教育環境が存在する。幕張は新都心として位置づけられ、スタジアムや商業施設といった開発が進み、かつて親しまれた干潟は失われてしまった。そこで、かつての干潟を再編集し、幕張のシビックプライドを再醸成させる教育環境としてのヒガタを提案する。

|
| br14083 樋室皓己人は、“そこにある”ことが当たり前となったとき、固有の価値を認識できなくなる。対象敷地は福岡県北九州市の中心都市・小倉。紫川はこのまちの発展を長きに渡って支え、人々の拠り所ともなっていた。しかし、時代の潮流とともに人々の意識から抜け落ち、さらにはこのまちへの愛着心すらも失われかけている。“そこにある”紫川で小倉の魅力をつむぎ、この場所ならではの固有の価値を再編し次代へとつなぐ。 |

br14091 村田次朗
ふらっとホーム -手段としての駅から目的としての駅へ-
人は他人同士の余計な干渉を避ける。情報化社会はそれを助長した。そしてひとりの人が増えた。対象は単身世帯の多い杉並区に位置する荻窪駅。だれもが通過するだけだった駅を家と捉えることで、ひとりになりたくない1人のためのサードプレイスを提案する。
人は他人同士の余計な干渉を避ける。情報化社会はそれを助長した。そしてひとりの人が増えた。対象は単身世帯の多い杉並区に位置する荻窪駅。だれもが通過するだけだった駅を家と捉えることで、ひとりになりたくない1人のためのサードプレイスを提案する。
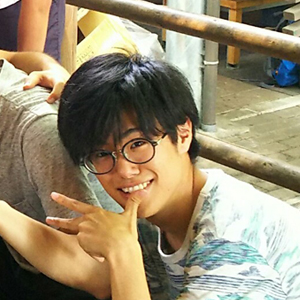
br14093 森天文
Autonomy in Work −同調からの脱却を促す建築−
近年働き方に注目が集まっている。「企業に勤めることによって未来が担保される時代」が終わり、多くの若者のキャリア観が個人主義的な「楽しさ」を求める傾向にある。内的な動機で仕事をする自律性をもった人間が脱工業化社会における「知」を獲得するためには必要である。日本では自律性よりも周りとの同調を図りがちであり、自律を阻む壁となっている。自律性を育み、そして解放できる場を提案する。
近年働き方に注目が集まっている。「企業に勤めることによって未来が担保される時代」が終わり、多くの若者のキャリア観が個人主義的な「楽しさ」を求める傾向にある。内的な動機で仕事をする自律性をもった人間が脱工業化社会における「知」を獲得するためには必要である。日本では自律性よりも周りとの同調を図りがちであり、自律を阻む壁となっている。自律性を育み、そして解放できる場を提案する。

br14095 山井冬華
武蔵野エリアにおけるActive-communityの生成とその変化の提案
都市のコミュニティの変化を仮想空間を置きシミュレートすることで起こりうる変化を可視化した。その結果を用い意図的に変化を促す設計を提案した。
都市のコミュニティの変化を仮想空間を置きシミュレートすることで起こりうる変化を可視化した。その結果を用い意図的に変化を促す設計を提案した。
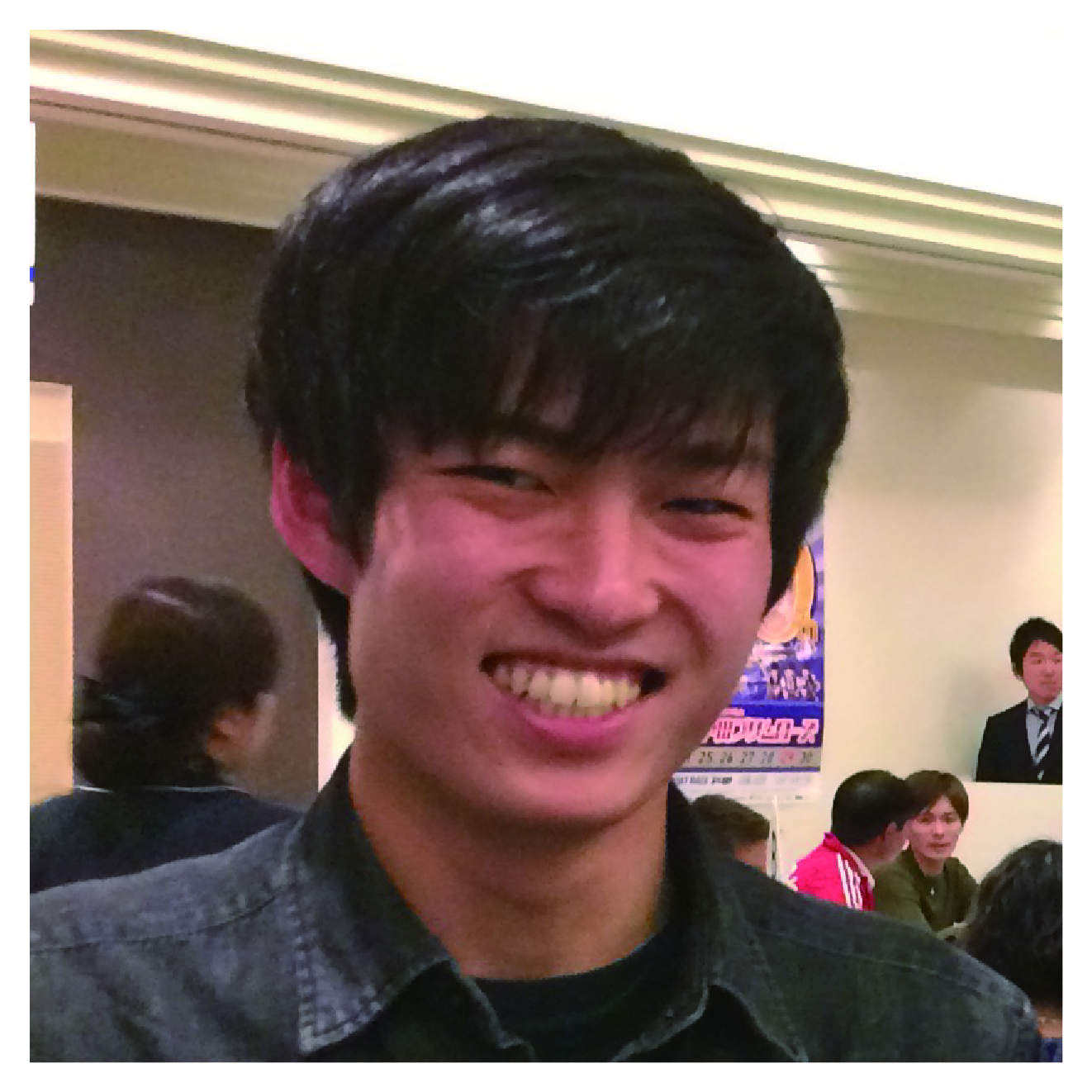
br14098 渡邊圭悟
Active Railway -見沼田んぼと鉄道のダイアローグ-
対象は埼玉県さいたま市にある「見沼たんぼ」と「東武アーバンパークライン」。地域を分断している鉄道を、「見沼田んぼ」という資源を利用して地域をつなげるものへと変える。これまで関わり合うことがなかった鉄道と沿線地域の接点を作り出すことで、「見沼田んぼ」と鉄道の対話(=ダイアローグ)を生み出す。
対象は埼玉県さいたま市にある「見沼たんぼ」と「東武アーバンパークライン」。地域を分断している鉄道を、「見沼田んぼ」という資源を利用して地域をつなげるものへと変える。これまで関わり合うことがなかった鉄道と沿線地域の接点を作り出すことで、「見沼田んぼ」と鉄道の対話(=ダイアローグ)を生み出す。
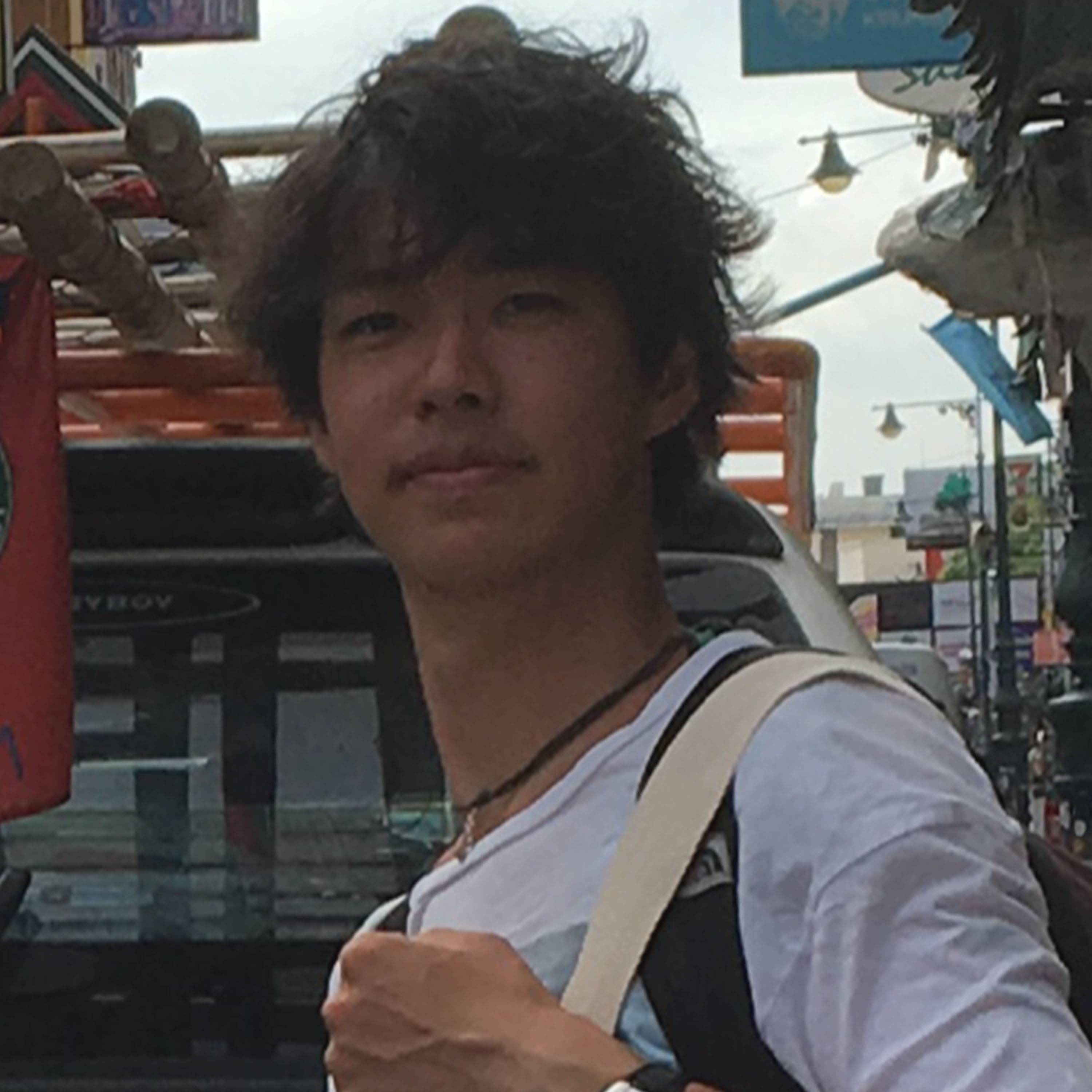
br14100 渡辺裕太
団欒の在り処-住宅都市のもう一つの居場所-
現在にかけて日本では人口の減少と共に核家族や単身者の世帯が増加している。家族が個人にまで分解され、個々の様々な生活の在り方によってかつてあった団欒を失いかけている。時代の流れによって決められた機能の住居形態だけではコミュニティは対応しきれない。このような様々な世帯にとっての生活にサードプレイスを加えることで、人々や地域にとってのコミュニティの新たな価値を構築する。
現在にかけて日本では人口の減少と共に核家族や単身者の世帯が増加している。家族が個人にまで分解され、個々の様々な生活の在り方によってかつてあった団欒を失いかけている。時代の流れによって決められた機能の住居形態だけではコミュニティは対応しきれない。このような様々な世帯にとっての生活にサードプレイスを加えることで、人々や地域にとってのコミュニティの新たな価値を構築する。
■デザイン工学科
| image | overview | ||
|---|---|---|---|
 |
cy14006 梅津和樹統合失調症と呼ばれる疾患がある。かつて精神分裂症と呼ばれたこの疾患は100人に1人の割合で発症すると言われており、決して珍しい疾患ではない。しかし、統合失調症に対する誤解や偏見は根強く残っており、精神医療を受け再び社会に復帰する人たちの受け皿は整っていない。横浜の谷戸という地形に注目し、患者と社会が積極的に関わるようなプログラムを建築に付与することで横浜における新しい精神医療のあり方を提案する。 |
||
 |
cy14009 小倉今日子シェアハウスやカーシェアリングに代表されるように「シェア」と呼びうる動きは、現代社会の様々な局面で生起しつつある。「シェア」は空間や物の占有方法に大きな変化をもたらそうとしている。本設計においては都市と田舎の二拠点において「シェア」の可能性を探る。地域が抱える問題は様々であり、都市部では薄れていくコミュニティに目を向け、郊外においては新天地における人間関係の構築を目指して設計を行う。 |
||
 |
cy14010 小野智也私の実家は江戸時代から続く、染色業を営んでいる。しかし、それは廃れ始め、存亡危機に瀕している。悲しいことにそれが伝統工芸品大国の現状である。伝統工芸品は身近なものでなくなりながらも、そのままの形式を保存することが求められる時代である。その固まりきったこの業界にはあらゆるものとの新たな関係性が必要であると考える。それらが絡み合い、一つの街のきっかけとして芽吹いていくこと望む。 | ||
 |
cy14013 崔希峰東日本大震災では津波により多くの建物が壊滅的な被害を受けた。今後大規模な地震発生に伴い、甚大な津波被害が予想される地域において津波からの一次避難施設として津波避難ビル等の指定・普及が必要と考える。 静岡県沼津市をケーススタディとし、近隣住民や観光客などが日常から利用出来るソフトと港湾地区のランドマーク的存在になりえるハードを兼ね備えた津波避難ビルの提案を行う。 |
||
 |
cy14015 嶋津崇靖典型的な地方都市の衰退をみせる静岡県浜松市。同市の同規模で比較的賑わう静岡市との比較より、市街地における憩える都市軸を創出する。暗渠の鉄道高架沿いは、新旧の浜松市街地を分断する曖昧な境界。この河川再生より境界をより明確に 。足場がヒントの構造体を河川沿いにのばし、境界上を蛇行する低層の空間を設計する。境界は市民の憩える都市軸へ変貌し、平面的回遊は都市を新たな視点から見直す機会となる。 |
||
 |
cy14017 調知征対象敷地である福岡県朝倉市は、私の祖父が幼少期に住んでいた地であり、田園風景が広がる農業が盛んな町である。私の祖先たちはこの地に家を持ち代々住み続けたが、現在は誰も住んでおらず空き屋状態となっている。祖父の思い入れが深いこの家を後世に残せるよう、地域になじむような建物を設計する。この地で感じた空虚感を学童と駐在さんと地域の人々を絡めたシステムでにぎわいを持たせようと試みた提案である。 |
||
 |
cy14018 関華子インターネットの普及により、商業都市として栄えた都市は衰退の一途を辿っている。一方で、中心市街地の裏街区には暫定的な土地利用として駐車場が多く見られるようになった。本設計では、都市の持続を図るために、中心市街地の裏街区を 中心に再開発が行われるまでの暫定的な土地利用を提案する。“シェア”をテーマに貸店舗と公共空間を設計し、その都市を訪れる人々がまちに参加し、まちを味わえるような空間を目指した。 |
||
 |
cy14021 髙橋侑平ダムや堤防のような頑丈なインフラを整備してきた日本であるが近年問題になっている局地的な大雨に対応することができていない。この一つの要因に住人の水防意識の低下が考えられる。敷地は、愛知、岐阜、三重の県境に位置する岐阜県海津市。この土地は、輪中地帯として有名であり、人々は水害と戦ってきた歴史のある土地である。ここに日常的に水防意識を高め、災害時には復興の拠点となる建築、ランドスケープを提案する。 |
||
 |
cy14022 高山啓少子高齢化、人口減少時代に対する適応策をテーマとし、これらの問題が深刻化すると推定される江戸川区において提案を行う。少子高齢化によって今後、交通弱者の増加と生産人口の減少が見込まれる。人口は次第に公共交通の便の良い駅周辺 へ集中する。そのためのコンパクトシティの形成が必要であると考え、地域の特徴の一つである工場の土地利用転換を再考し、実在の敷地において駅周辺に都市の機能を補完する拠点を提案する。 |
||
 |
cy14027 中田安美近年、市街地開発による子供の居場所の減少に伴って小学生の放課後の過ごし方に変化が見られる。かつては外遊びが主流だったが、自由に遊べる環境が失われた現代は塾や習い事に通う子供が増えている。そこで本設計では、人工的に作られた起伏のある地形「丘」に習い事が行われるスタジオと遊び空間を挿入することで、遊びの経験不足問題を解消し、更に市街地に住む | ||
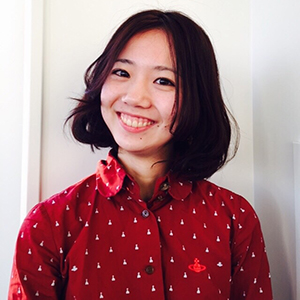 |
cy14030 庭山ありさ利便性を求めて集まって住むという価値観ではなく、疎に住み自然とふれあうという価値観で集合住宅を設計した。敷地は調布市と小金井市の境にある公園に挟まれた土地で豊かな自然環境と生態系の保全のために低層低密な住環境と、この土地で昔から慕われてきたホタルを保全するホタル観察センターを設計した。住宅は今後住み方や人の密度が変化する事を前提に混構造で設計し、ホタル観察センターは生態的特徴を生かす設計にした。 |
||
 |
cy14031 長谷川輝世仮設はある限られた期限を持つが、この仮設は、まちの財産である美しい川辺で季節に対応しながら地元の人たちの手によって変化し、ともに遷移していく。毎年変化する川辺の風景が今後のまちの観光にも、その土地に根を張るまちづくりにも つながっていく。地方都市の少子高齢化対策や住みやすいまちの創出を目指す。人と人が新たに出会い、人と自然と時間を共にする公共商業施設と仮設建築による交流空間。 |