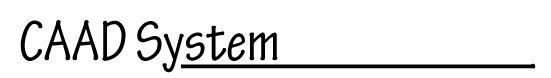デザインの戦略
デザインの戦略
 光に関する言説
光に関する言説


 デザインの戦略
デザインの戦略
・・・これは、およそ建物は分離認識可能で、しかも関係づけられた要素の集合と見なしうるという観念に基づいていた。それらの要素を私は次のように規定した。
1)計画内容、すなわち完全な有機体組織の持つ要求や性能の根拠となる機能的関係性の図解的表現。
2)敷地、および敷地が建物や用地に与える影響
3)入り口と動線方式。この場合の動線方式は建物本体だけに限らず適用されるものとする。
4)組成方式としての構造
5)構造方式に関連する壁の系統が規定する外皮もしくは被膜。
さらに、入り口と動線方式、外皮と構造、計画内容と敷地の間には弁証法が存在したのである。
こうした語法による分析は、物理的環境の秩序という概念を扱う作品の共通事項および特殊事項をも露呈することにあった。それは一種の「道徳律」であって、多元的批評あるいは私の作品に対する形態中心主義、選良主義といった当節流行の批評に対する一つの返答であった。私が語っていたのは、計画内容に対する形態の関係性であった。しかしながら、基本的関心は形態の関係であったのだ。・・・

 光に関する言説
光に関する言説
・・・自然光は私にとって、また私の作品にとってとても重要なのです。その光が創り出す移ろいやすさには何よりも関心があります。建築家としての私にとっての特別な挑戦は、空間をどのように照明すべきかという問題に多くがあるのではなく、与えられた環境と状況のもとで、光をいかに制御するかにあります。当然のことながら、光を現実の、ソリッドな材料として扱うことは出来ません。瞬間的なエレメントですから。実際とても不思議なもので、光の可能性を学ぶには、光を実際に扱ってみるほかないのです。何かをする、すると何かが起こる。ところがほんの少しするとほかの何かが起こるのです。
・・・外の世界の、光、色彩、雰囲気の変化を知覚する可能性を持たないということは、私には人生の質という点において非常な損出だと思えるのです。建築においては、光は、建物の持つある種の構造的アイデアを強化します。それ自身の構造を持っているものとしては光をみていません。人工照明はもちろんのことです。光が演ずべき仕事は、既存のもの、表面、空間を支援し、アクセントを付け、開くことです。私の白い色に対する傾き、そしてその色が他の全ての色を含み、吸収しているという事実は、この考えをよく説明しています。
・・・私はまた、ルイス・カーンが何度も言っていたように、空間は、自然の光なしには、建築の内に存在する場所というものには決して到達できないということを信じています。自然光の予測不可能な演技に比肩し得る何かがあるだろうか。建築は空間と、思慮に満ちた、意味深い、空間をつくることと関わっています。自然光は空間に雰囲気を与え、季節ごとに年間を通して、また日々に変わる光のニュアンスによって、空間を修飾し、分節します。その空間は静かであり、それでいて生命感に溢れているのです。