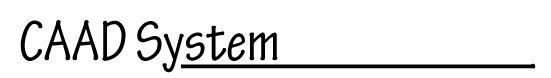
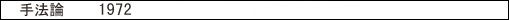 1960年代の磯崎の言説が「空間へ」のなかにまとめられるにあたり、それまでの自身の
近代建築批判を乗り越えるべく書かれた論文。
60年代を通じて、建築に対する提案が軌を一にして統合を拒否し、断片化し、無形式化
し、虚像となり、不可視な領域とかかわりはじめたのは、もはや総体の状況が近代建築
が内包してきた統一性をもった規薄をうけつけなくなったことの反映に他ならず、革新
的に新しい視覚言語を出現することが絶望視されたとき、現代建築は「出口」を探そう
とした。その「出口」の一つは、建築を都市の領域まで拡張し、巨大建築物をつくるこ
と、もう一つは、ヴァナキュラリズムと総称されているような、他領域の土着言語を導
入することであった。
磯崎はこの論文を通じて、近代建築あるいはそれまで磯崎自身が生み出してきた主題に
破産宣告を告げる。近代建築は、鉄、コンクリート、機械に自ら宇宙観を投影し、工法
からデザインに至るまで工業化を浸透させ、一つの視覚言語の系にまで洗練させること
に成功したが、今日の科学技術の発展を考えると、建築において表現すべき物質的形態
は、使い勝手、機能、生活の道具、シェルター、ガラス、プラスチック等、無数に至る
所にころがっている。
しかし、現在のような混在系、モザイク的不連続な共生系の中でしか建築の設計がなさ
れないとするならば、単一系の理論を追究するのではなく、個別に開発された視覚言語
を組み合わせることが重要である。
磯崎は空間内に混在系を成立させるために「手法」を生み出した。自らの手法を整理し
「布石」、「切断」、「射影」、「梱包」、「転写」、「応答」、「増幅」という七つ
の側面から建築の構造を見ている。
この7つに共通して言えることは、いずれも、可視的領域のなかで、物体にひとつの形
態を与えるときに、その物体の独自の理論、すなわち客観性をもった近代科学的手続き
にこだわらずに、実存感を喪失させ、一つの形式に押しこめるようなとり扱いにかたむ
いている点である。
1960年代の磯崎の言説が「空間へ」のなかにまとめられるにあたり、それまでの自身の
近代建築批判を乗り越えるべく書かれた論文。
60年代を通じて、建築に対する提案が軌を一にして統合を拒否し、断片化し、無形式化
し、虚像となり、不可視な領域とかかわりはじめたのは、もはや総体の状況が近代建築
が内包してきた統一性をもった規薄をうけつけなくなったことの反映に他ならず、革新
的に新しい視覚言語を出現することが絶望視されたとき、現代建築は「出口」を探そう
とした。その「出口」の一つは、建築を都市の領域まで拡張し、巨大建築物をつくるこ
と、もう一つは、ヴァナキュラリズムと総称されているような、他領域の土着言語を導
入することであった。
磯崎はこの論文を通じて、近代建築あるいはそれまで磯崎自身が生み出してきた主題に
破産宣告を告げる。近代建築は、鉄、コンクリート、機械に自ら宇宙観を投影し、工法
からデザインに至るまで工業化を浸透させ、一つの視覚言語の系にまで洗練させること
に成功したが、今日の科学技術の発展を考えると、建築において表現すべき物質的形態
は、使い勝手、機能、生活の道具、シェルター、ガラス、プラスチック等、無数に至る
所にころがっている。
しかし、現在のような混在系、モザイク的不連続な共生系の中でしか建築の設計がなさ
れないとするならば、単一系の理論を追究するのではなく、個別に開発された視覚言語
を組み合わせることが重要である。
磯崎は空間内に混在系を成立させるために「手法」を生み出した。自らの手法を整理し
「布石」、「切断」、「射影」、「梱包」、「転写」、「応答」、「増幅」という七つ
の側面から建築の構造を見ている。
この7つに共通して言えることは、いずれも、可視的領域のなかで、物体にひとつの形
態を与えるときに、その物体の独自の理論、すなわち客観性をもった近代科学的手続き
にこだわらずに、実存感を喪失させ、一つの形式に押しこめるようなとり扱いにかたむ
いている点である。



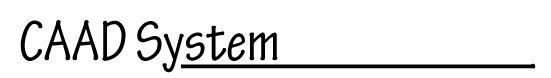
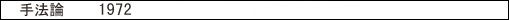 1960年代の磯崎の言説が「空間へ」のなかにまとめられるにあたり、それまでの自身の
近代建築批判を乗り越えるべく書かれた論文。
60年代を通じて、建築に対する提案が軌を一にして統合を拒否し、断片化し、無形式化
し、虚像となり、不可視な領域とかかわりはじめたのは、もはや総体の状況が近代建築
が内包してきた統一性をもった規薄をうけつけなくなったことの反映に他ならず、革新
的に新しい視覚言語を出現することが絶望視されたとき、現代建築は「出口」を探そう
とした。その「出口」の一つは、建築を都市の領域まで拡張し、巨大建築物をつくるこ
と、もう一つは、ヴァナキュラリズムと総称されているような、他領域の土着言語を導
入することであった。
磯崎はこの論文を通じて、近代建築あるいはそれまで磯崎自身が生み出してきた主題に
破産宣告を告げる。近代建築は、鉄、コンクリート、機械に自ら宇宙観を投影し、工法
からデザインに至るまで工業化を浸透させ、一つの視覚言語の系にまで洗練させること
に成功したが、今日の科学技術の発展を考えると、建築において表現すべき物質的形態
は、使い勝手、機能、生活の道具、シェルター、ガラス、プラスチック等、無数に至る
所にころがっている。
しかし、現在のような混在系、モザイク的不連続な共生系の中でしか建築の設計がなさ
れないとするならば、単一系の理論を追究するのではなく、個別に開発された視覚言語
を組み合わせることが重要である。
磯崎は空間内に混在系を成立させるために「手法」を生み出した。自らの手法を整理し
「布石」、「切断」、「射影」、「梱包」、「転写」、「応答」、「増幅」という七つ
の側面から建築の構造を見ている。
この7つに共通して言えることは、いずれも、可視的領域のなかで、物体にひとつの形
態を与えるときに、その物体の独自の理論、すなわち客観性をもった近代科学的手続き
にこだわらずに、実存感を喪失させ、一つの形式に押しこめるようなとり扱いにかたむ
いている点である。
1960年代の磯崎の言説が「空間へ」のなかにまとめられるにあたり、それまでの自身の
近代建築批判を乗り越えるべく書かれた論文。
60年代を通じて、建築に対する提案が軌を一にして統合を拒否し、断片化し、無形式化
し、虚像となり、不可視な領域とかかわりはじめたのは、もはや総体の状況が近代建築
が内包してきた統一性をもった規薄をうけつけなくなったことの反映に他ならず、革新
的に新しい視覚言語を出現することが絶望視されたとき、現代建築は「出口」を探そう
とした。その「出口」の一つは、建築を都市の領域まで拡張し、巨大建築物をつくるこ
と、もう一つは、ヴァナキュラリズムと総称されているような、他領域の土着言語を導
入することであった。
磯崎はこの論文を通じて、近代建築あるいはそれまで磯崎自身が生み出してきた主題に
破産宣告を告げる。近代建築は、鉄、コンクリート、機械に自ら宇宙観を投影し、工法
からデザインに至るまで工業化を浸透させ、一つの視覚言語の系にまで洗練させること
に成功したが、今日の科学技術の発展を考えると、建築において表現すべき物質的形態
は、使い勝手、機能、生活の道具、シェルター、ガラス、プラスチック等、無数に至る
所にころがっている。
しかし、現在のような混在系、モザイク的不連続な共生系の中でしか建築の設計がなさ
れないとするならば、単一系の理論を追究するのではなく、個別に開発された視覚言語
を組み合わせることが重要である。
磯崎は空間内に混在系を成立させるために「手法」を生み出した。自らの手法を整理し
「布石」、「切断」、「射影」、「梱包」、「転写」、「応答」、「増幅」という七つ
の側面から建築の構造を見ている。
この7つに共通して言えることは、いずれも、可視的領域のなかで、物体にひとつの形
態を与えるときに、その物体の独自の理論、すなわち客観性をもった近代科学的手続き
にこだわらずに、実存感を喪失させ、一つの形式に押しこめるようなとり扱いにかたむ
いている点である。


